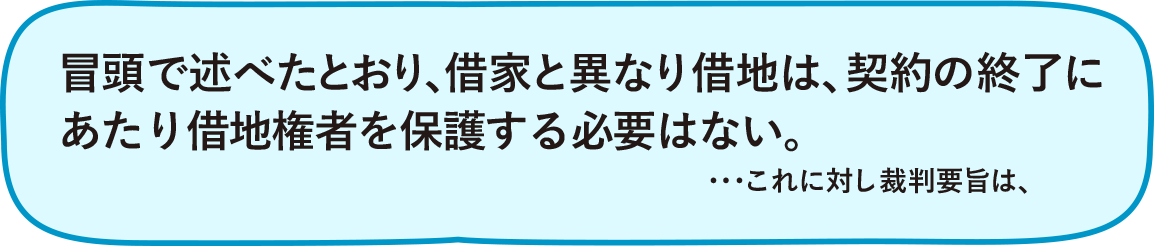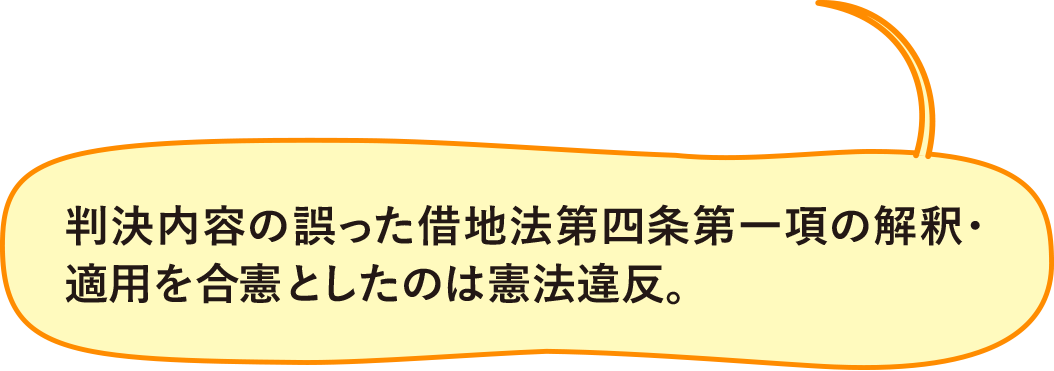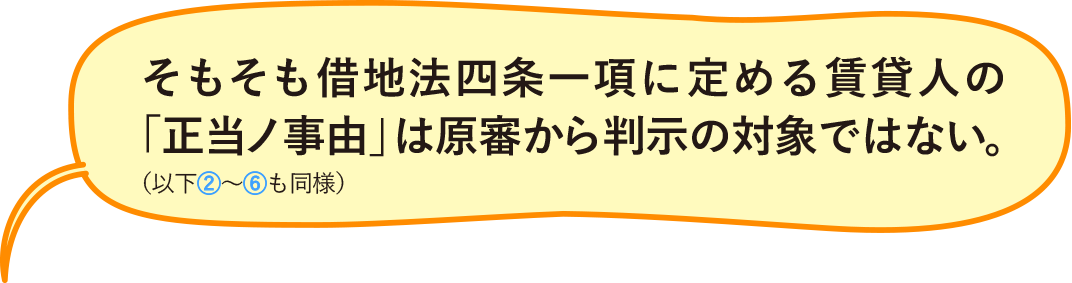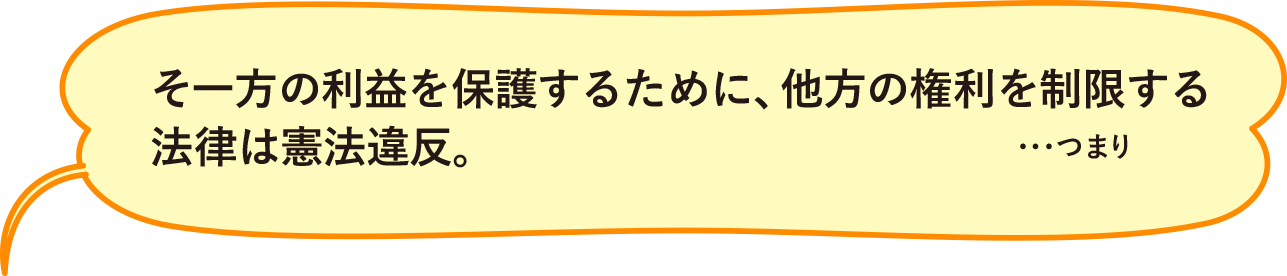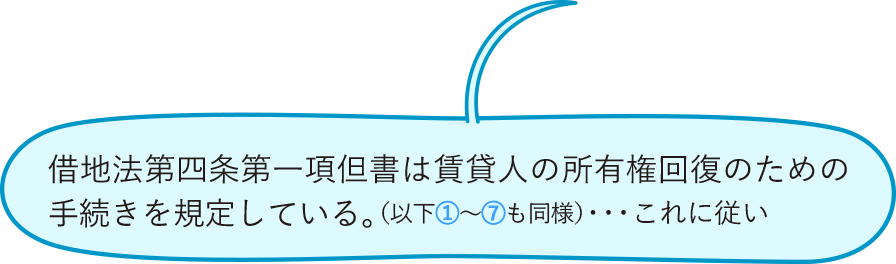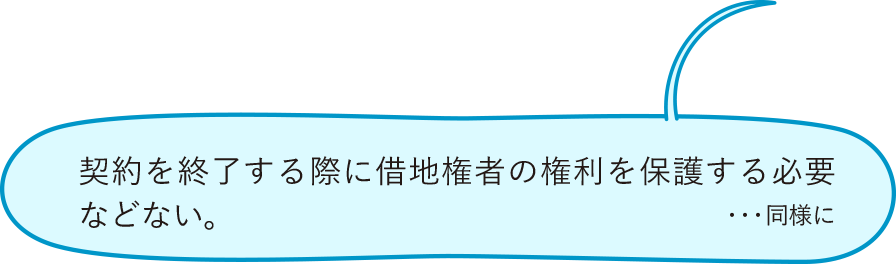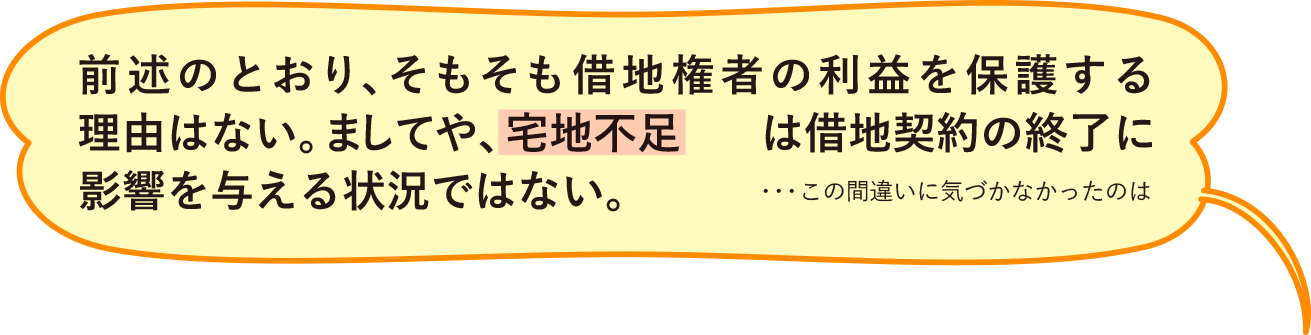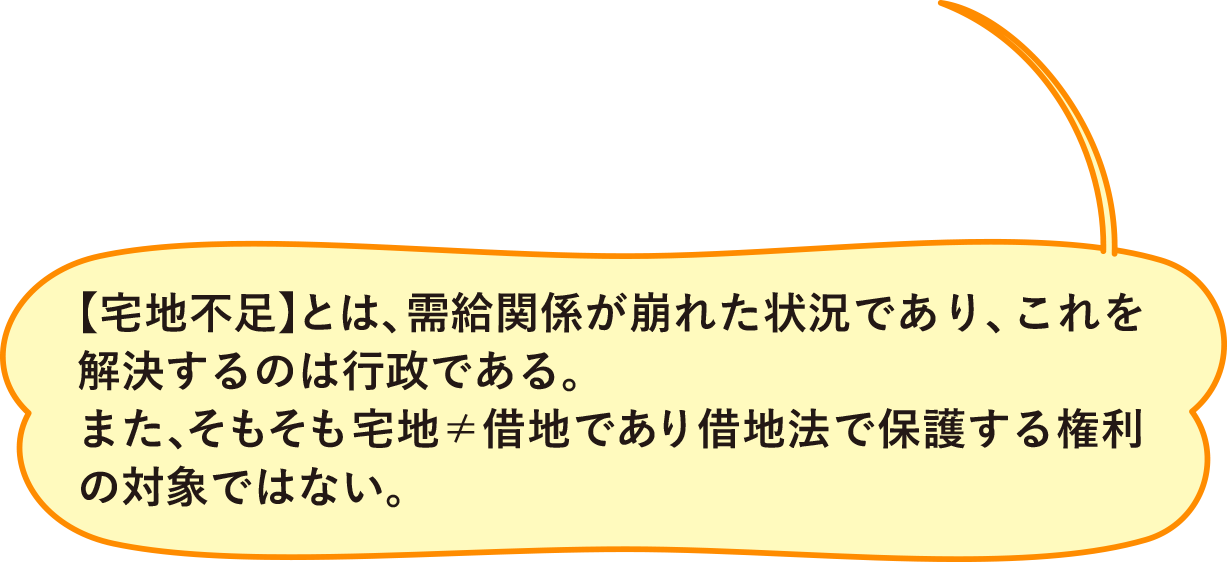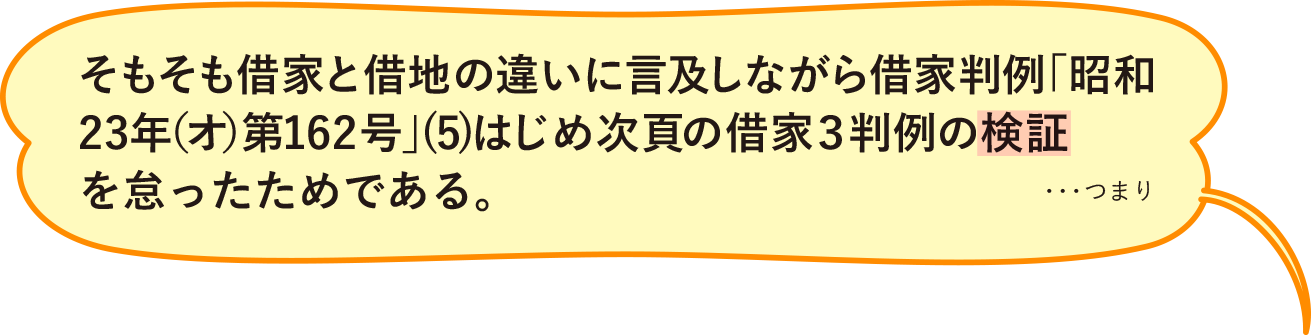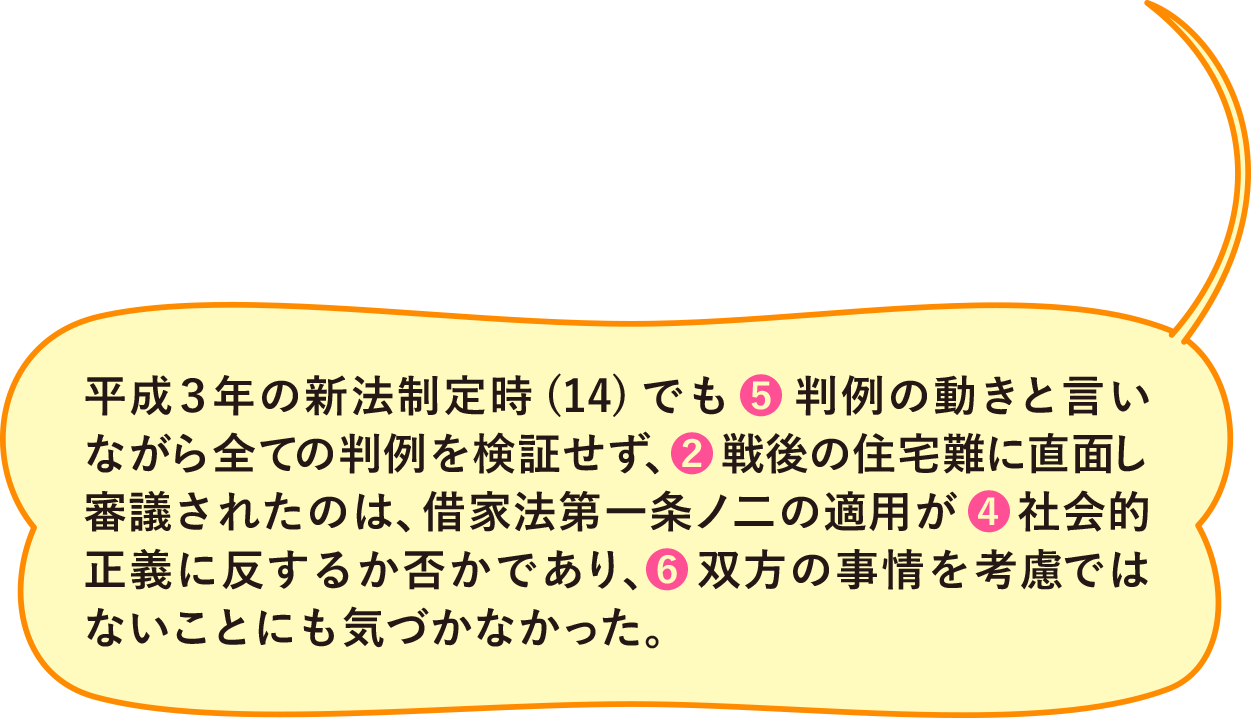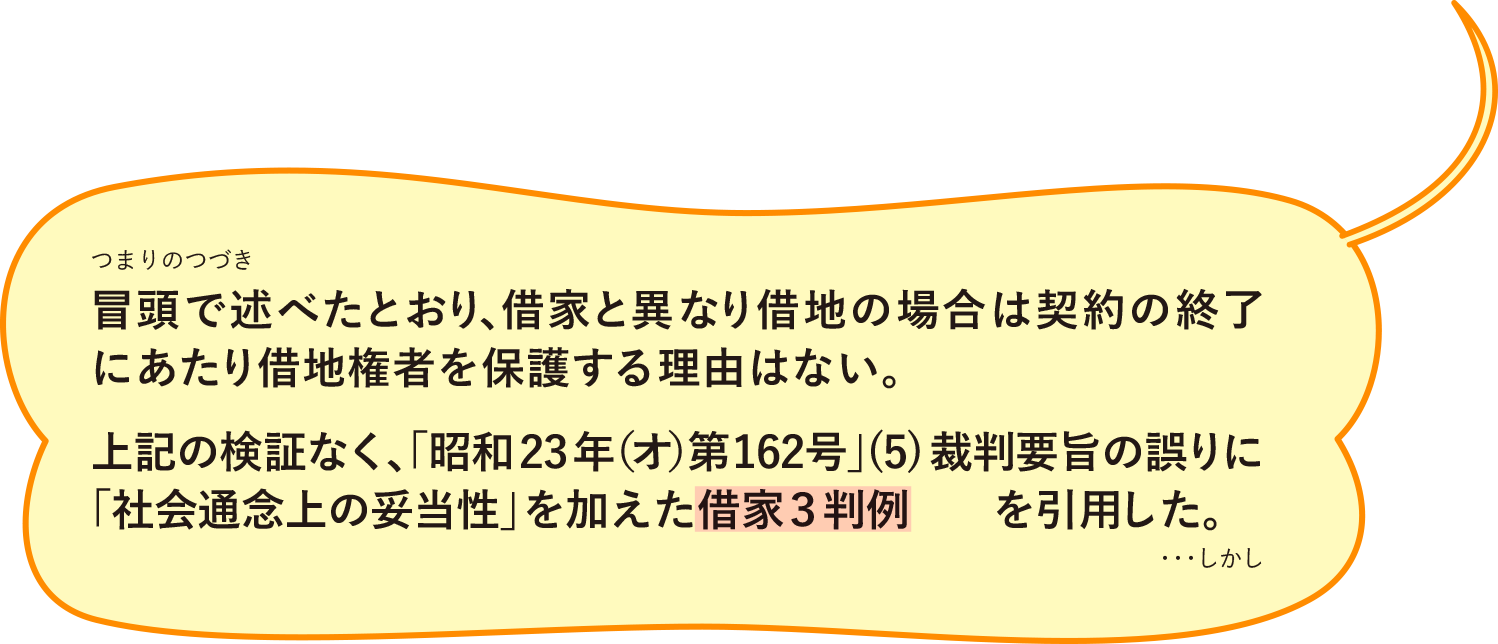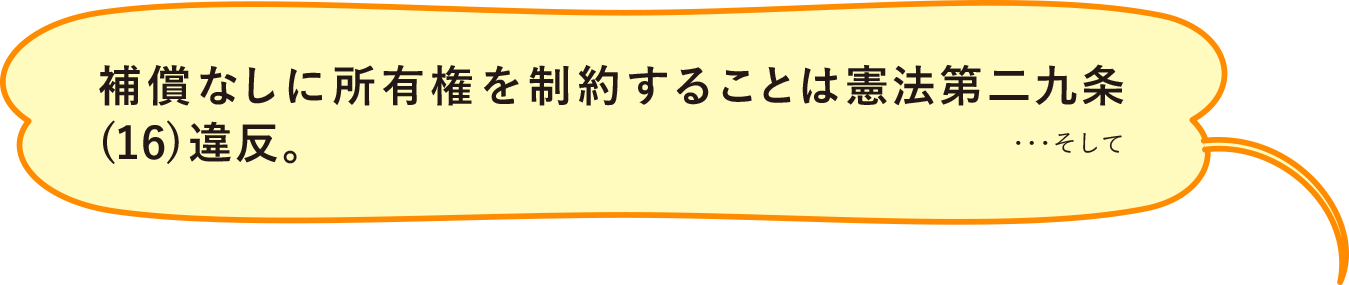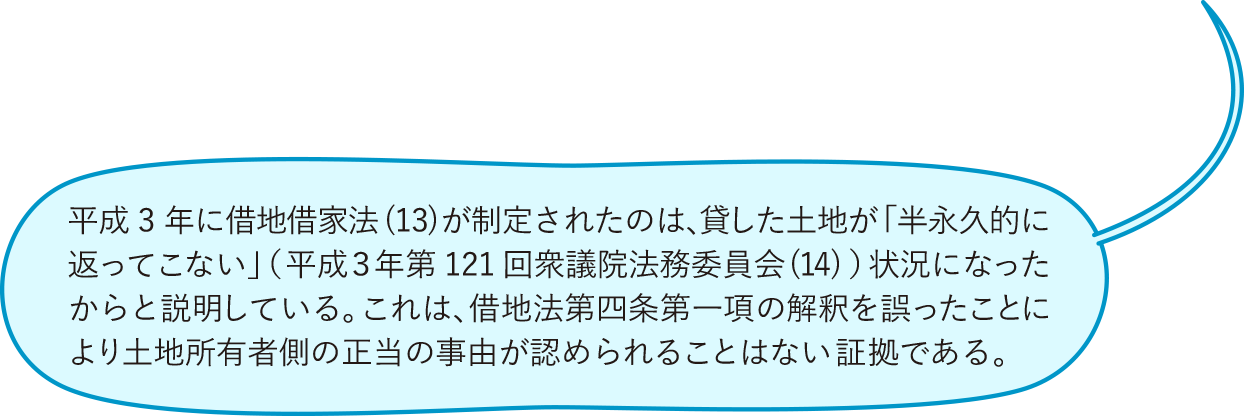借家と借地を混同し借地法の解釈をゆがめた最高裁
昭和34年(オ)第502号
意見広告でも述べたように、大法廷の最大の誤りは借家同様に「双方の事情を勘案」を借地にも踏襲し、借地法第四条第一項の解釈をゆがめたことである。
先の検証のとおり、借家の場合は借家法第一条ノ二を適用せずに借家人の権利(生存権)を保護したのは一時的に住宅難だったからである。これに対し、後述するように借地の場合はそもそも借地権者の権利を保護する理由はない。しかし、最高裁は前例の借家判例の検証を怠り、借家と借地を混同したことに気づかなかった。
以下では、大法廷が引用した借家3判例を含め前例の検証を行い、「昭和34年(オ)第502号」の誤りについて指摘する。
先の検証のとおり、借家の場合は借家法第一条ノ二を適用せずに借家人の権利(生存権)を保護したのは一時的に住宅難だったからである。これに対し、後述するように借地の場合はそもそも借地権者の権利を保護する理由はない。しかし、最高裁は前例の借家判例の検証を怠り、借家と借地を混同したことに気づかなかった。
以下では、大法廷が引用した借家3判例を含め前例の検証を行い、「昭和34年(オ)第502号」の誤りについて指摘する。
検証のまとめ
大法廷は、「昭和23年(オ)第162号」はじめ前例の借家判例に大きく依存し、借家と同様に借地権者の保護が必要とした。この誤った借地法の解釈・運用が裁判規範となり、昭和41年の一部法改正につながった。
以下では、大法廷判決を前提に、国家権力が借地借家関係に介入することを認めた法改正の審議過程と成立した条項を検証する。