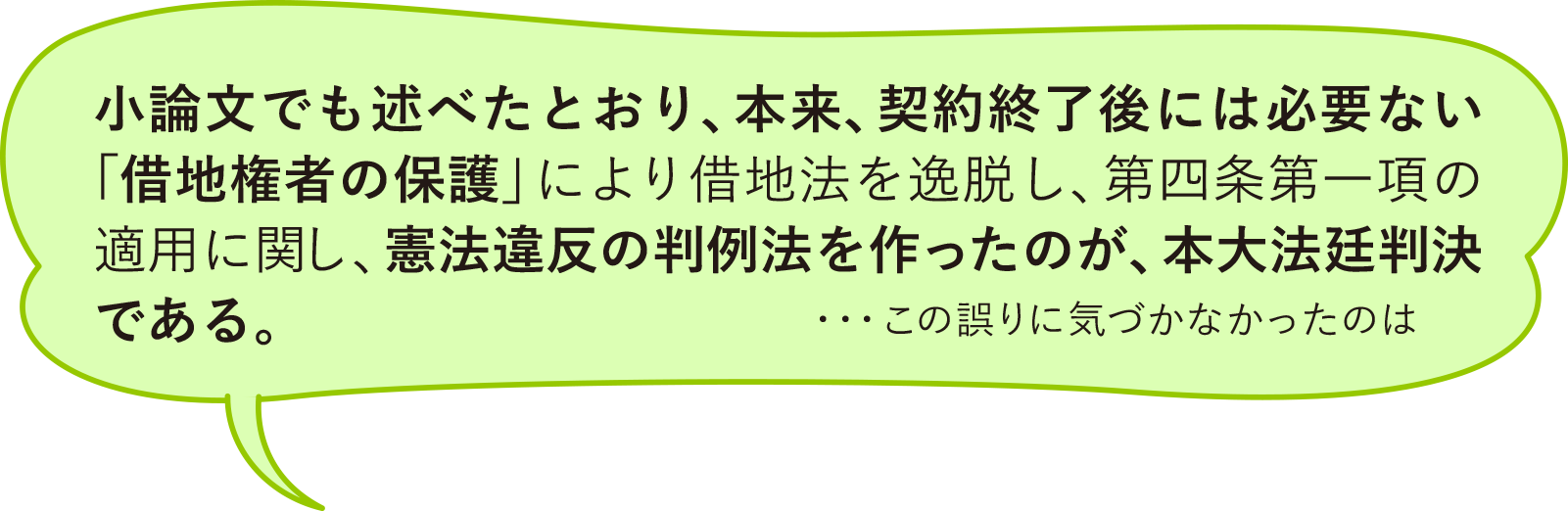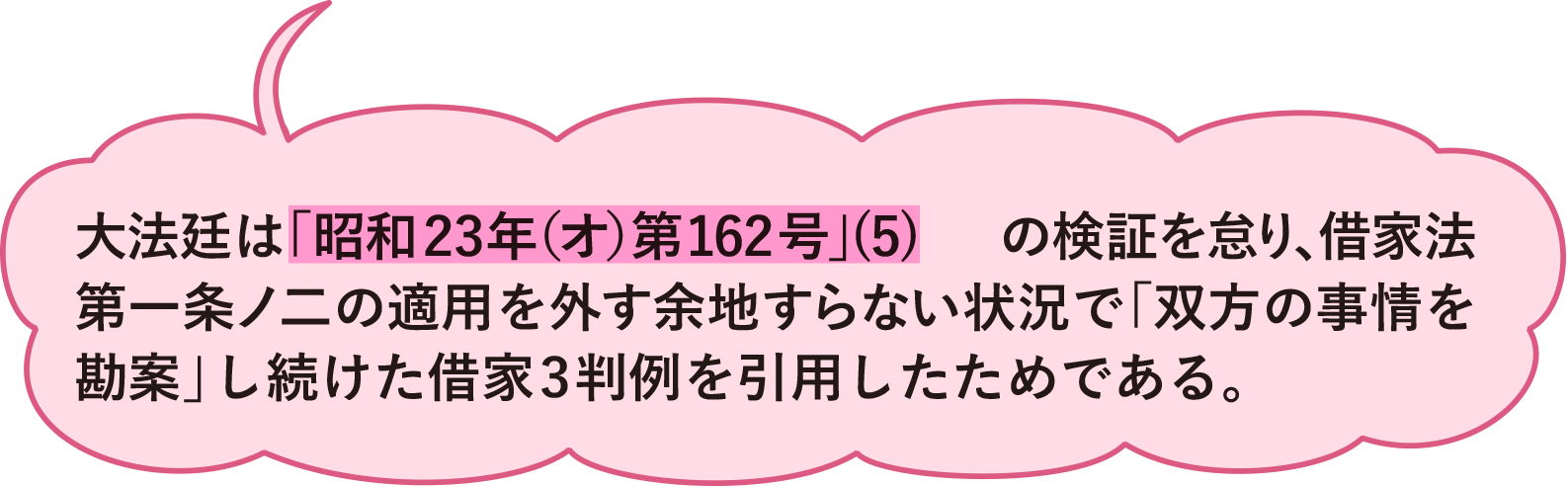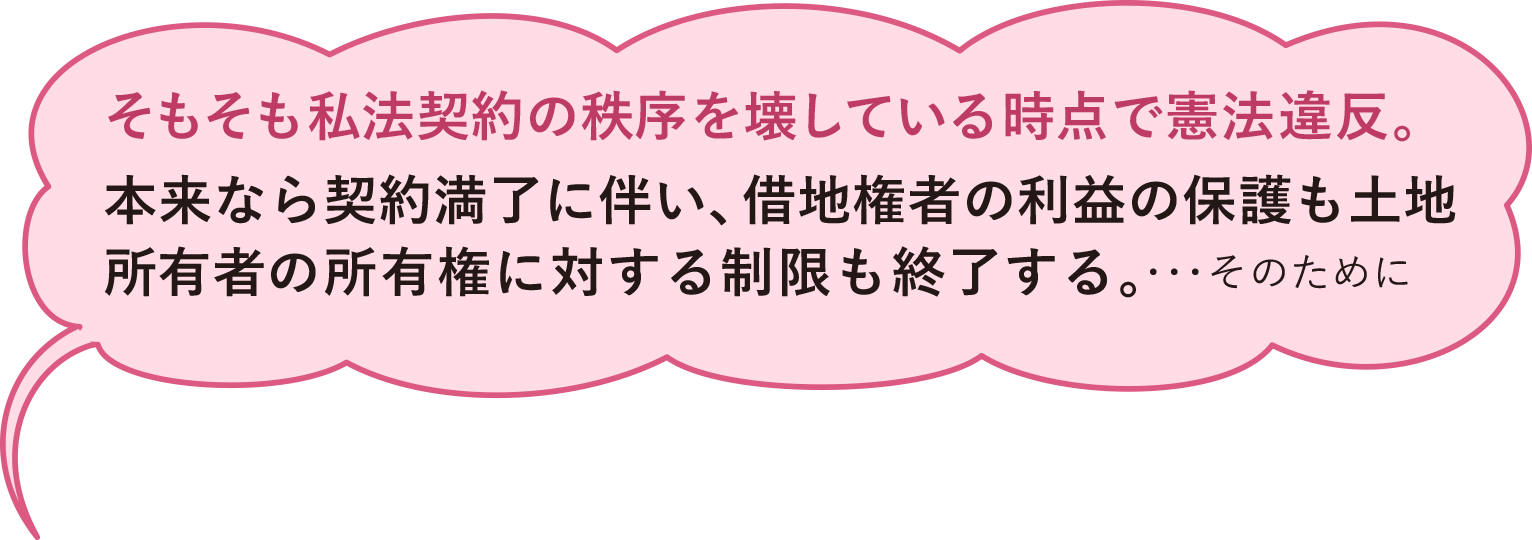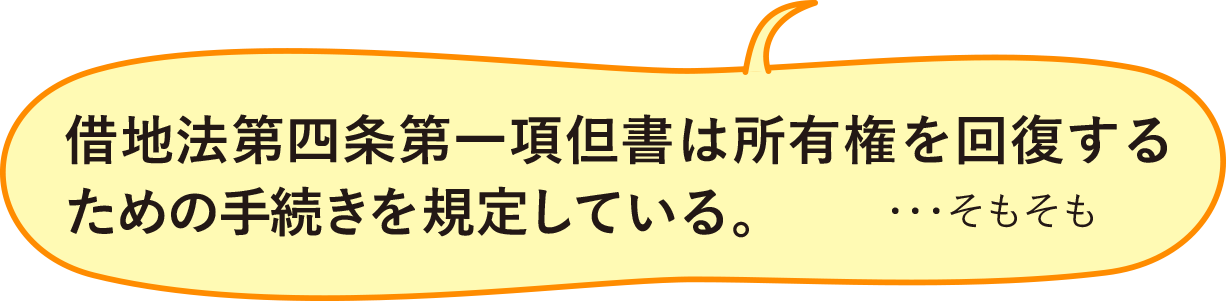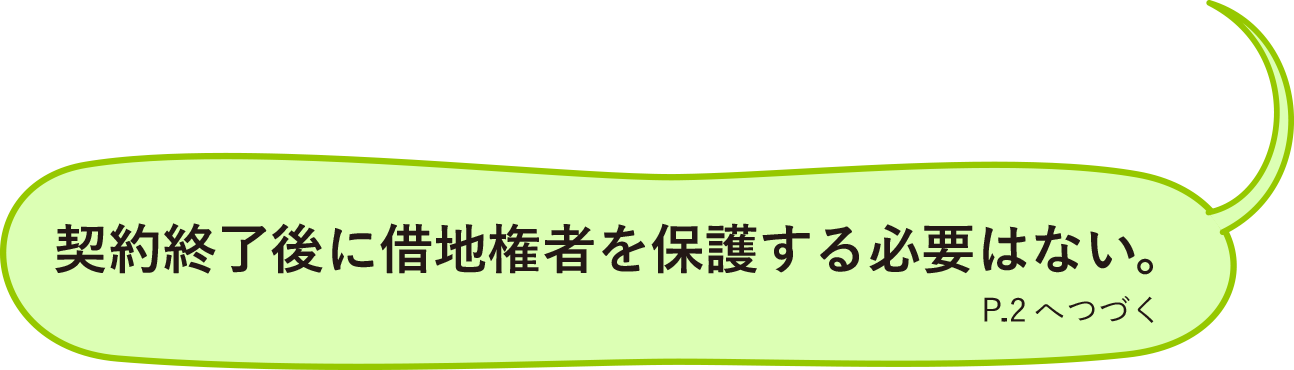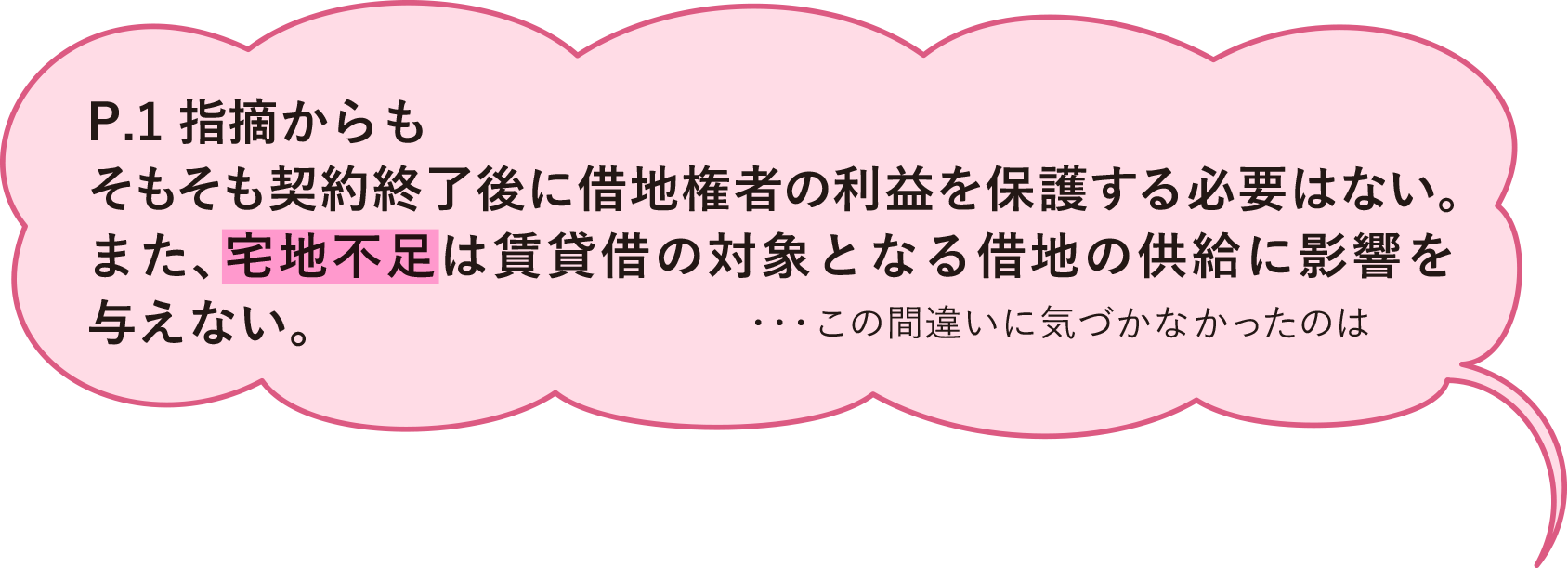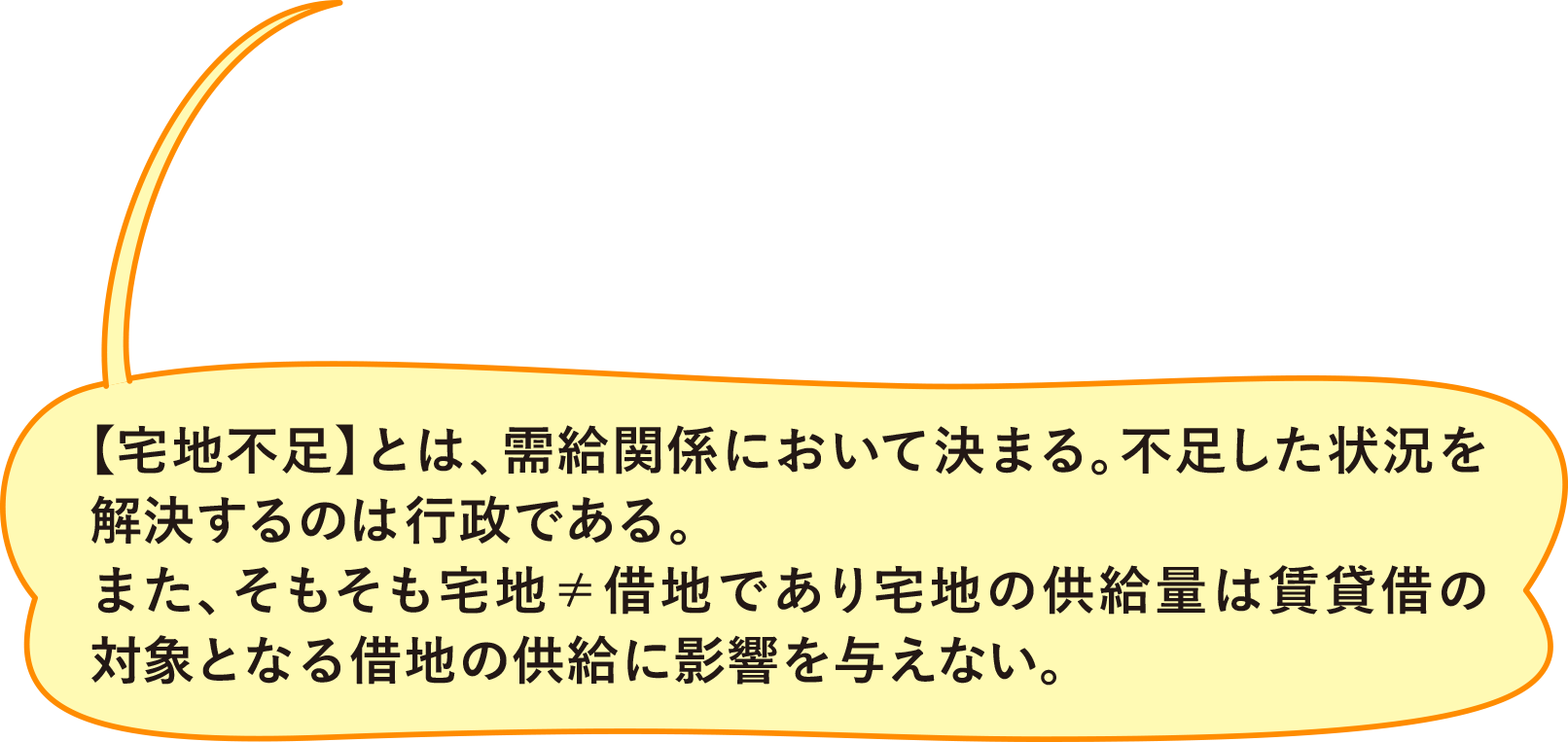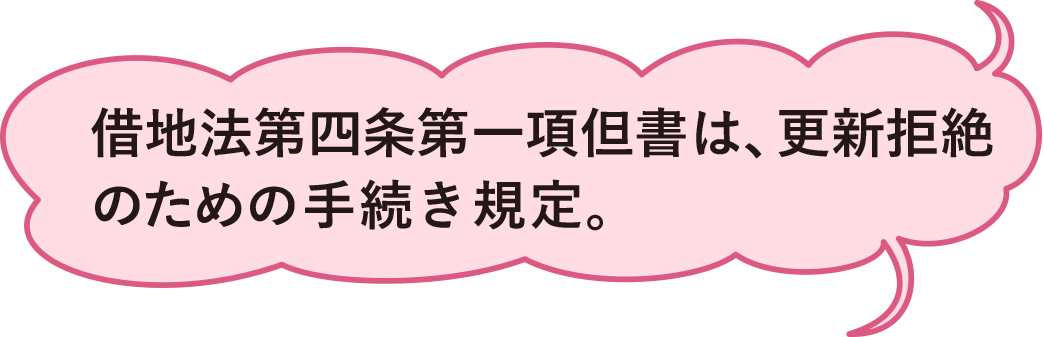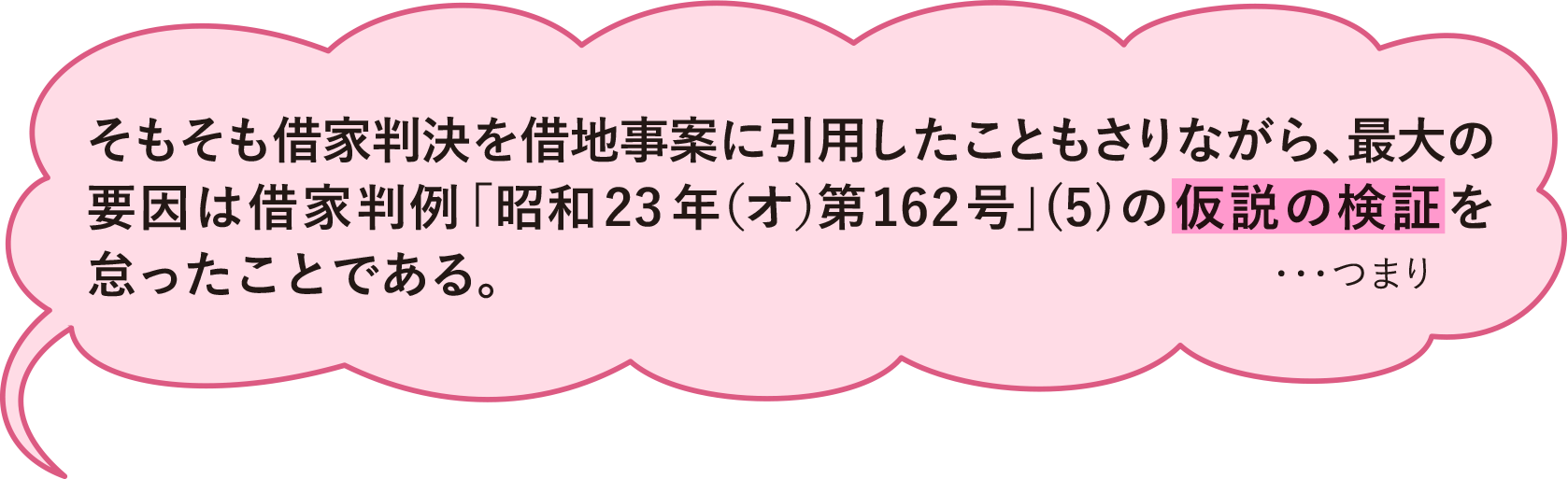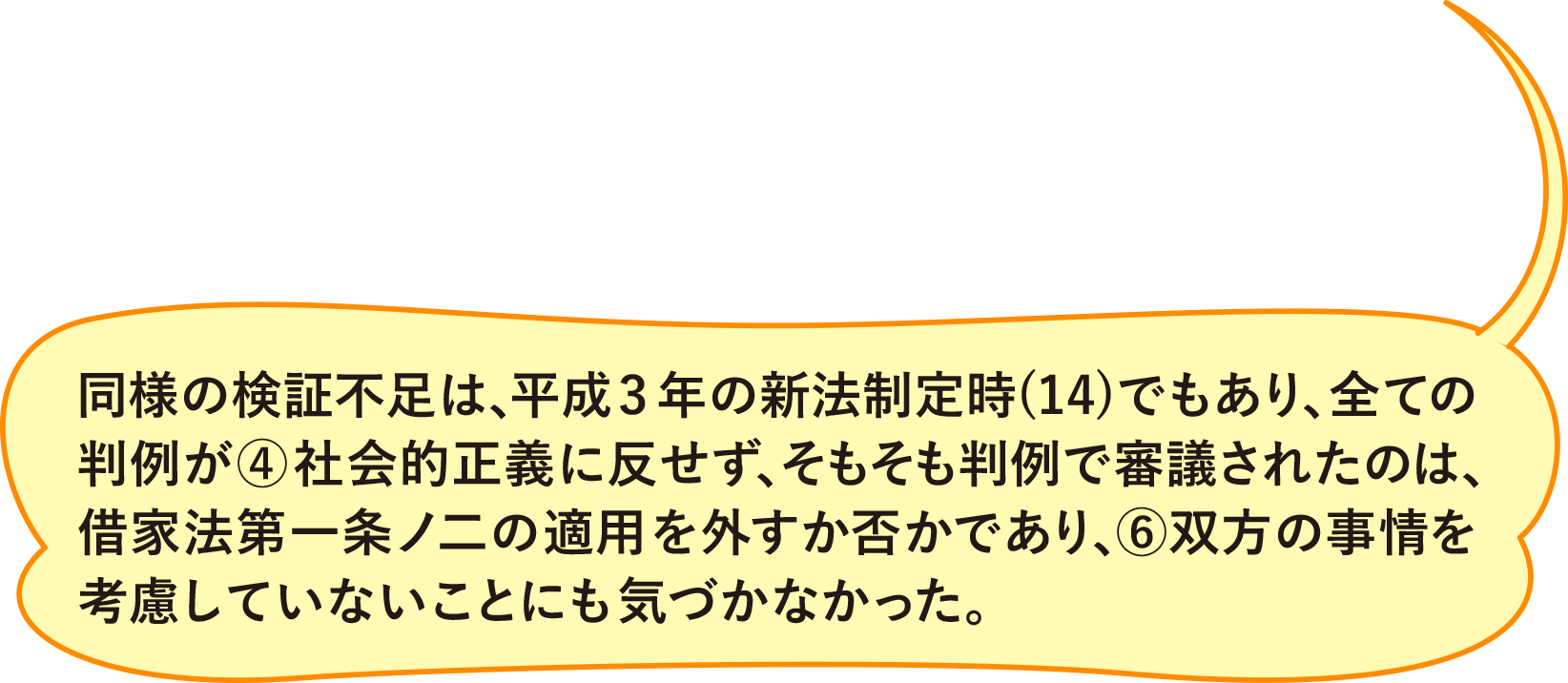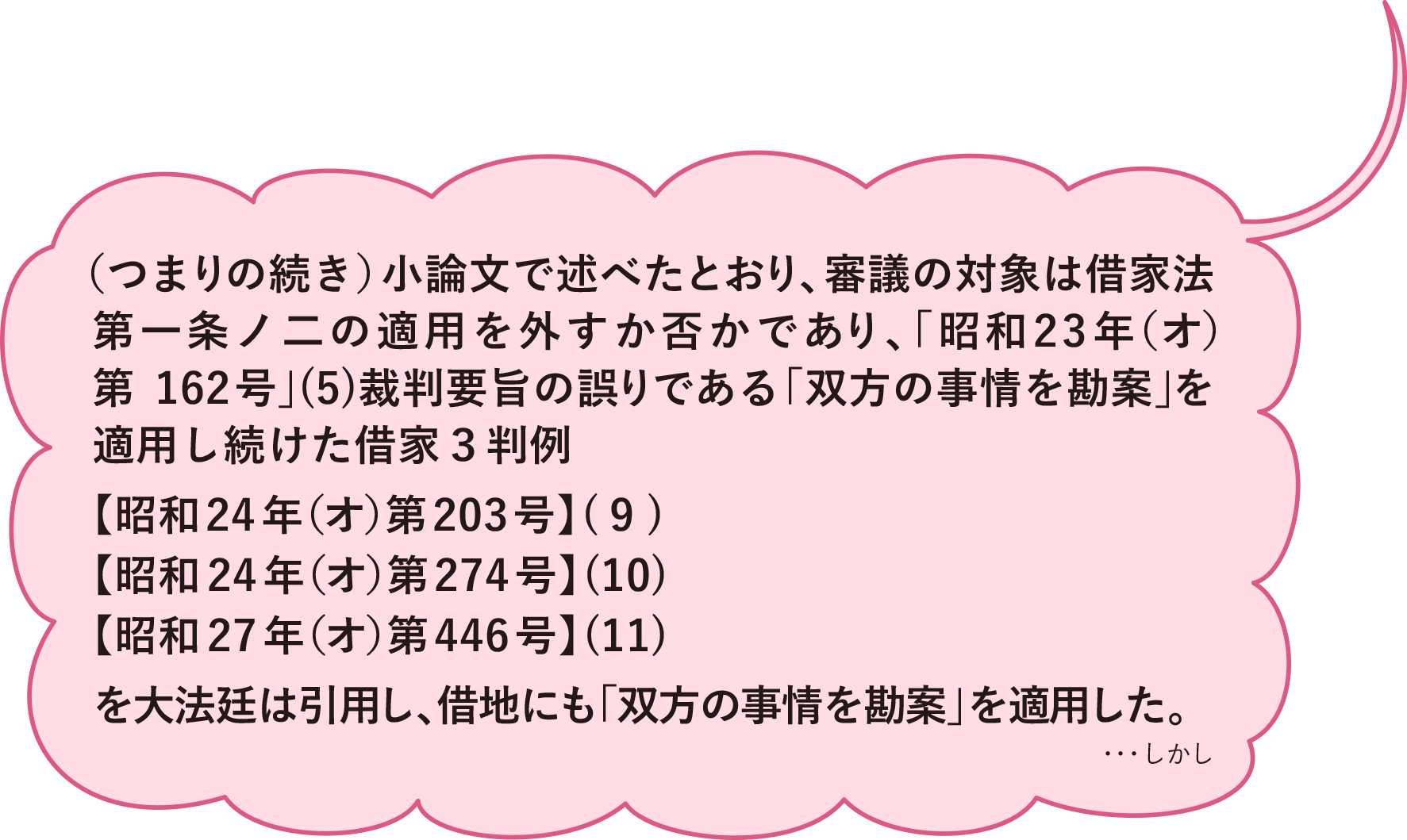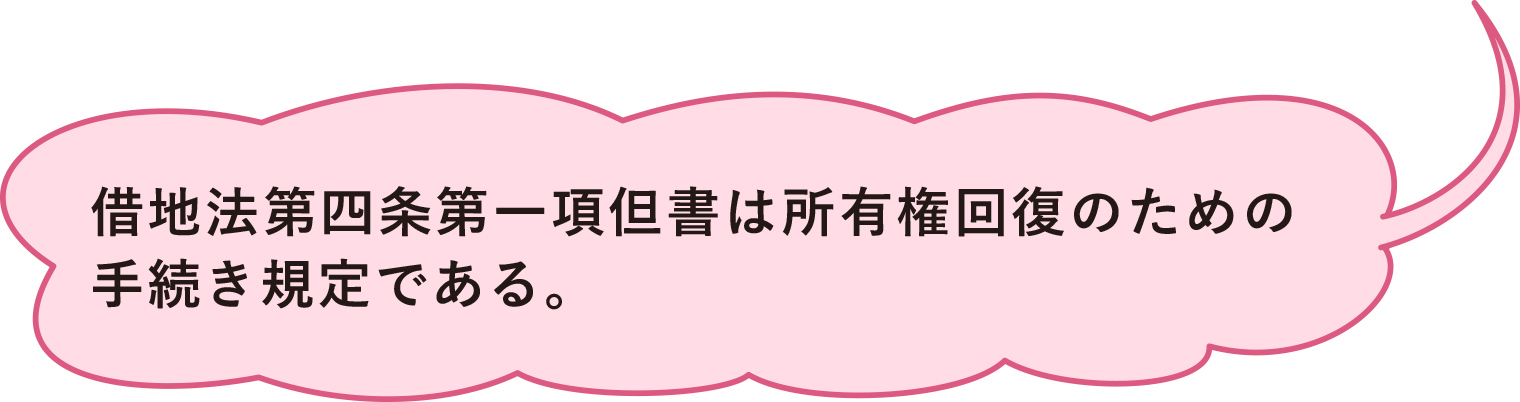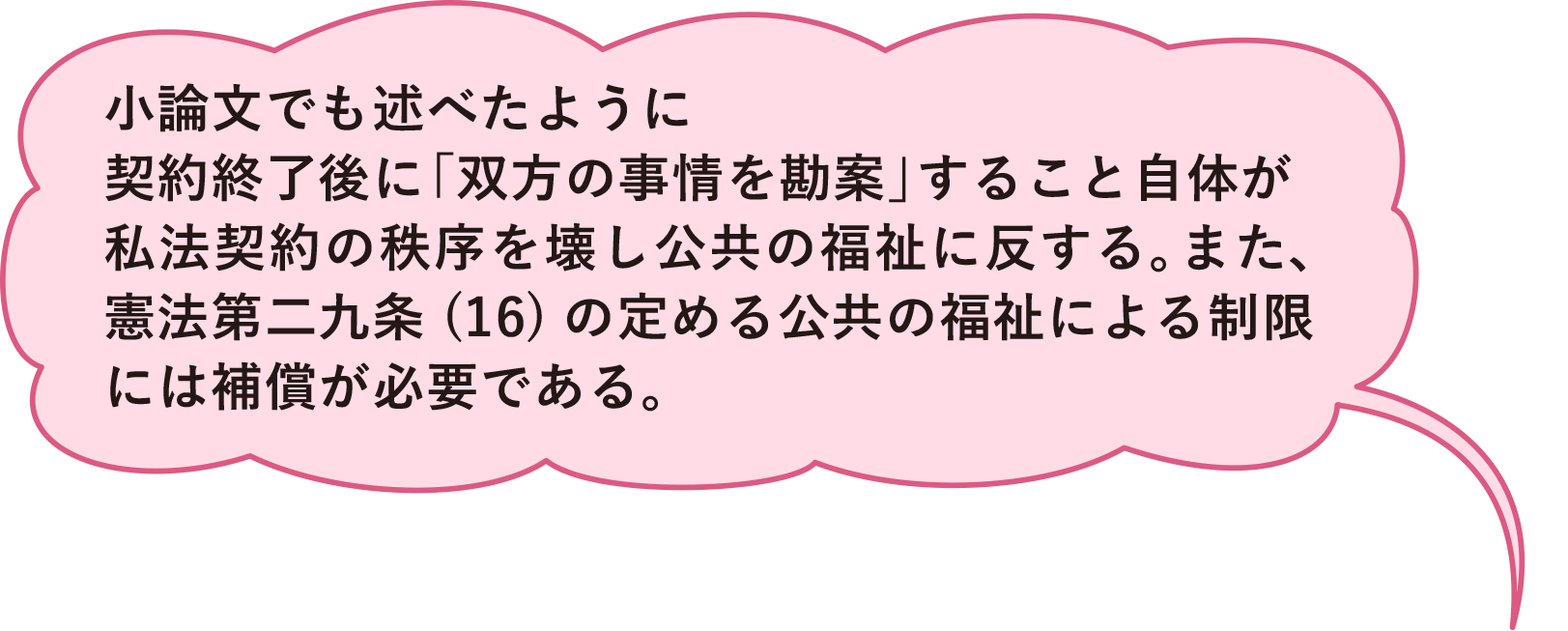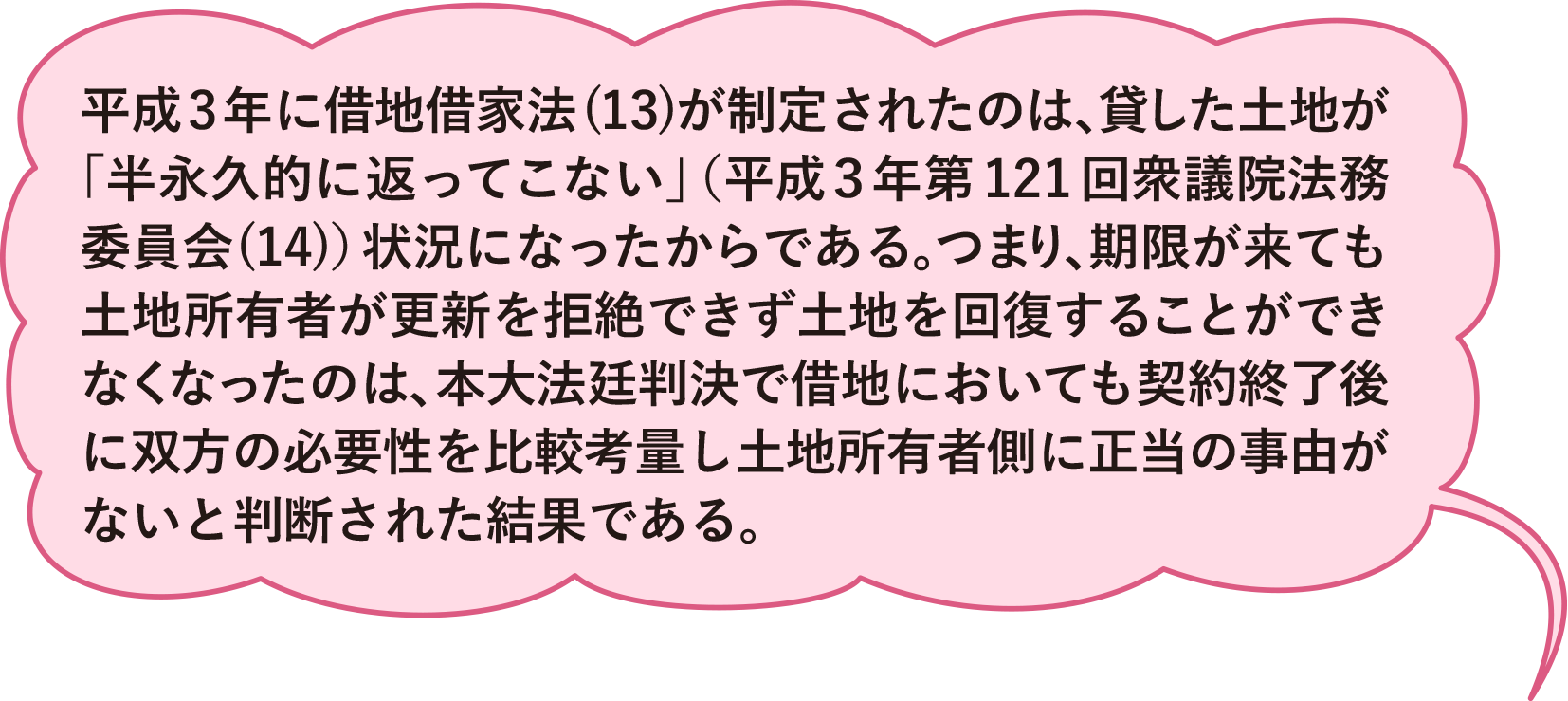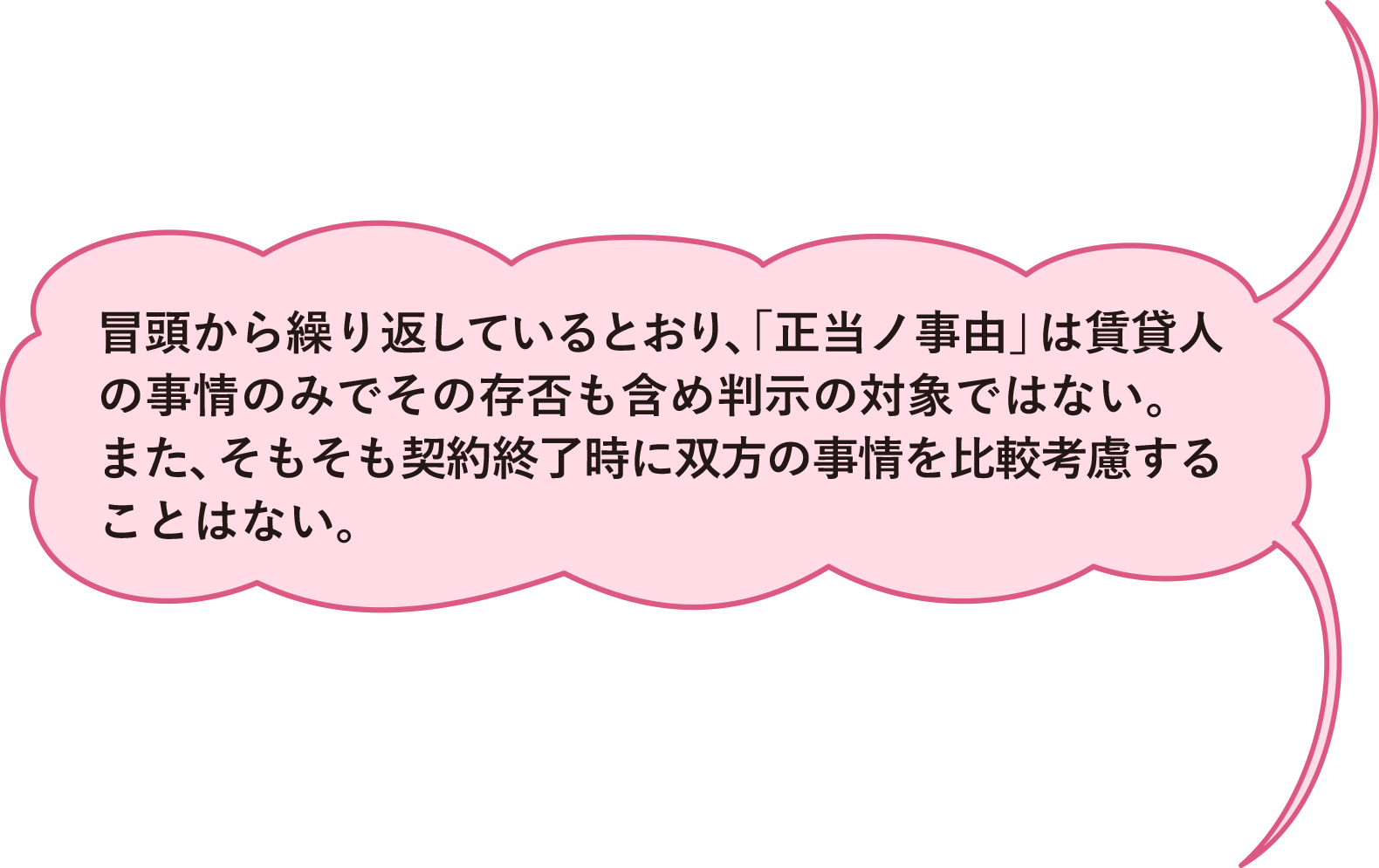昭和34年(オ)第502号
< 小論文 >
前例を検証する責務を怠り、憲法違反の裁判規範を定立した最高裁
昭和34年(オ)第502号
- 意見広告でも述べたように、前例の借家判例に大きく依存して、借地法の立法趣旨とは異なる裁判規範を定立したのが、本大法廷判決「昭和34年(オ)第502号」である。
-
先の検証のとおり、戦後の住宅難に直面し、借家法第一条ノ二を適用するか否かを審議した借家判例と異なり、借地の場合はそもそも借地法第四条第一項の適用を外す立法事実は存在しない。従って、理由の如何を問わず契約終了後に借地権者の保護をした本判決は憲法違反である。
以下では「昭和23年(オ)第162号」はじめその後の借家判例の検証を怠ったため、大法廷自身が気づけなかった誤りにつき検証する。
昭和34年(オ)第502号:まとめ
大法廷は、「昭和23年(オ)第162号」はじめ前例の借家判例に大きく依存し、借家と同様に借地の場合にも契約期限後の借地権者の利益の保護が必要とする裁判規範を定立した。そして、この立法趣旨とは異なる借地法の運用を裁判要旨で合憲とし、やがて「終わらない借地契約」を生み出したのである。
大法廷が定立した憲法違反の裁判規範は見直しも修正もされるどころか、それを前提に土地の合理的な使用を目的に、国家権力が私人間の契約関係に介入することを認める法改正が昭和41年に行われたのである。
大法廷が定立した憲法違反の裁判規範は見直しも修正もされるどころか、それを前提に土地の合理的な使用を目的に、国家権力が私人間の契約関係に介入することを認める法改正が昭和41年に行われたのである。