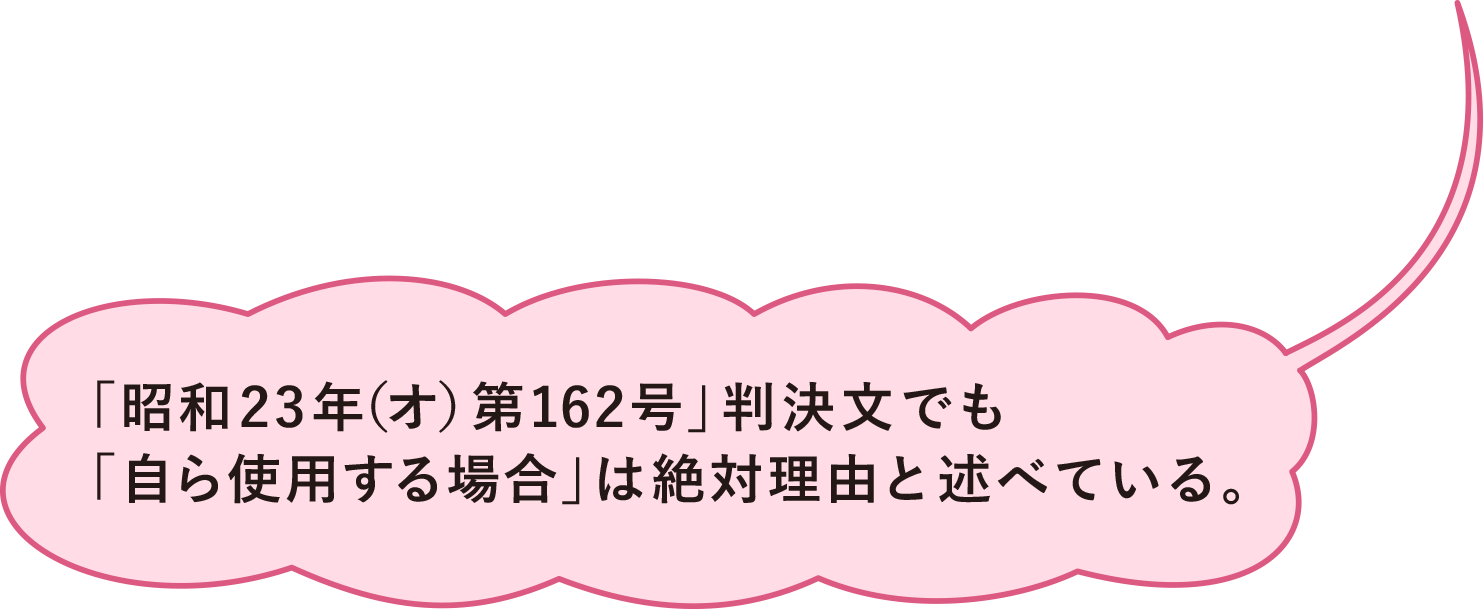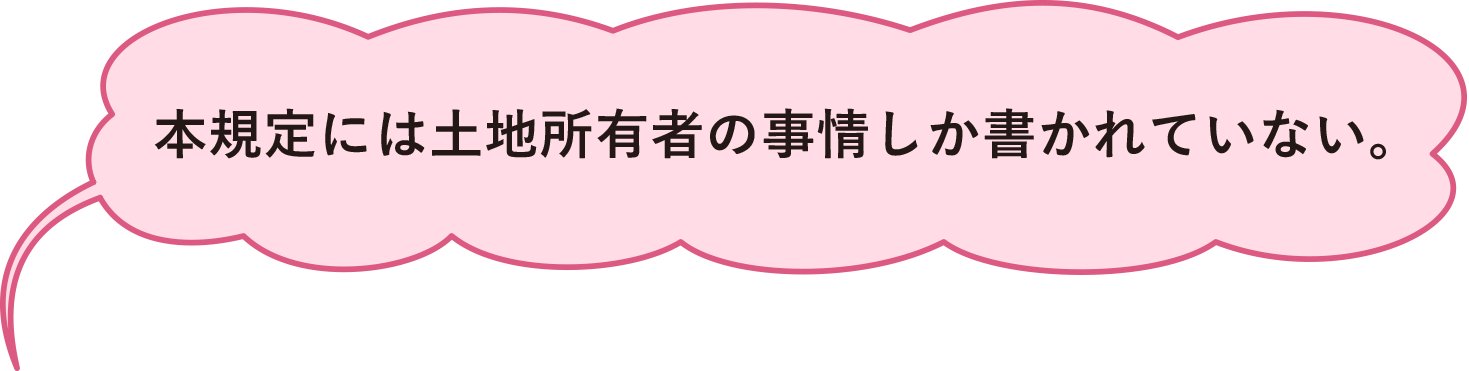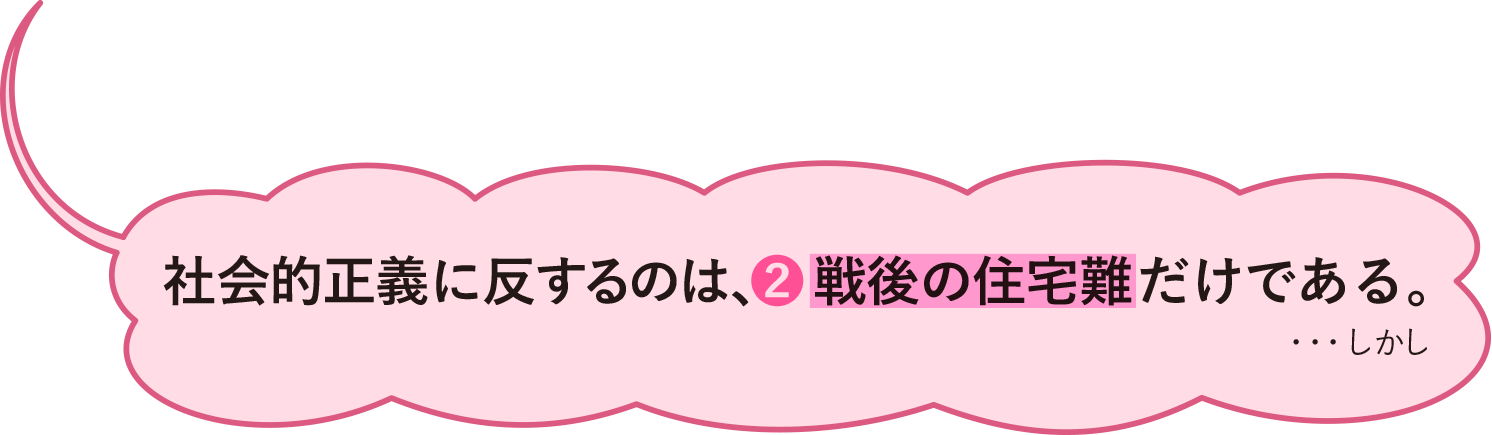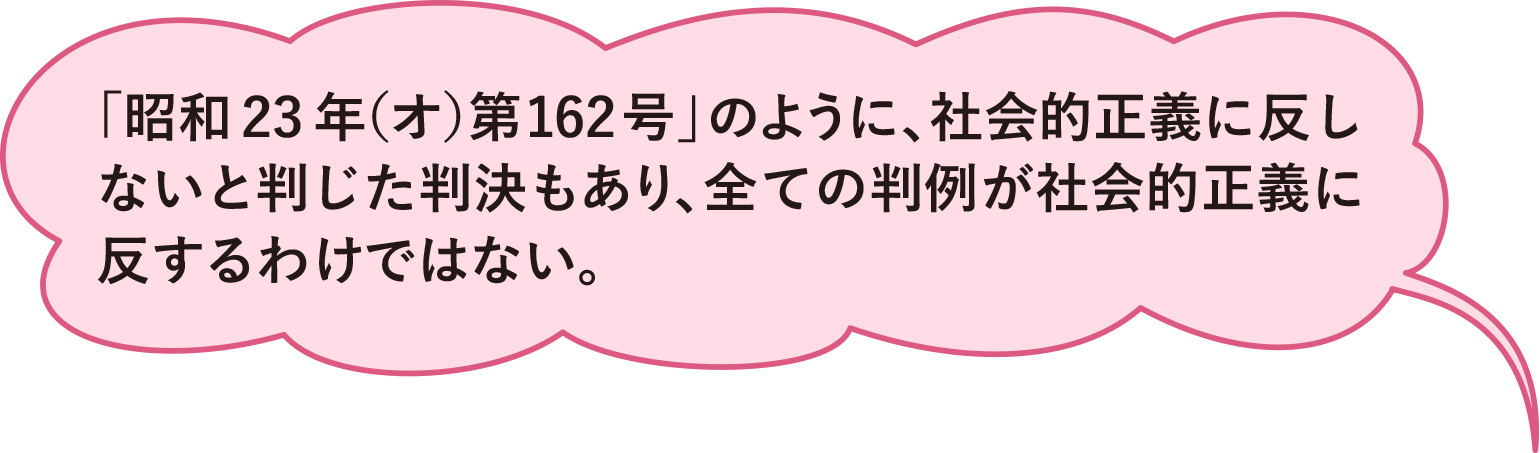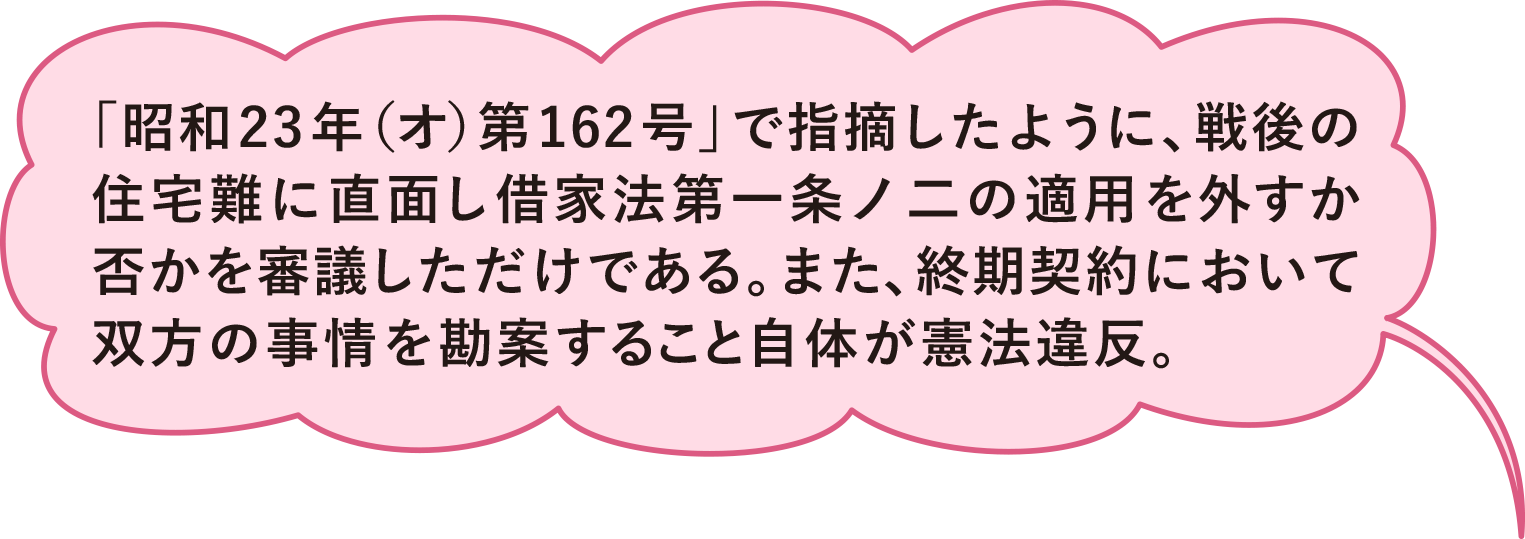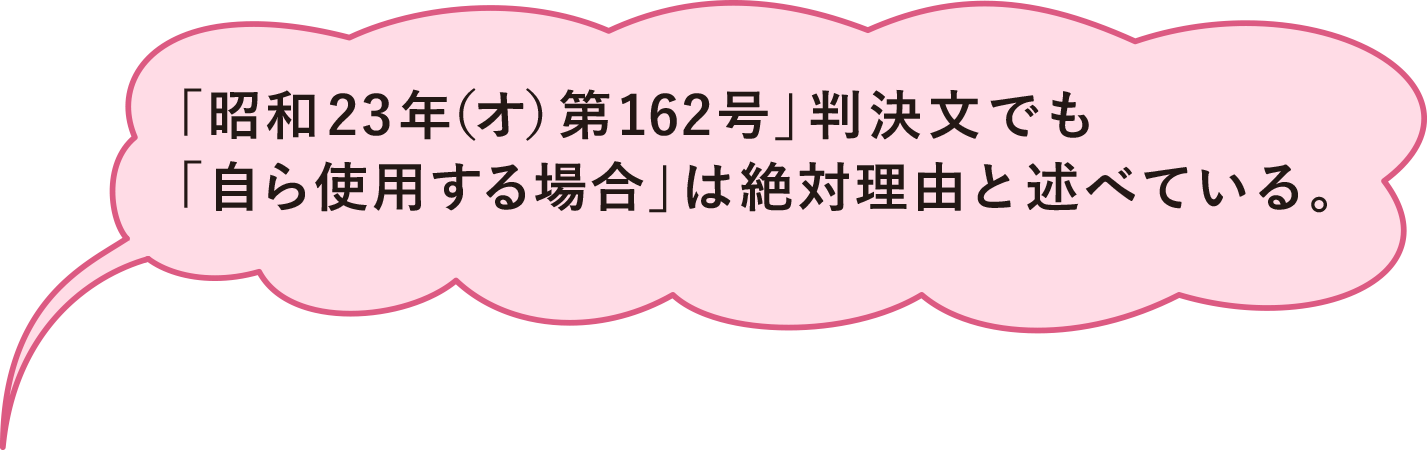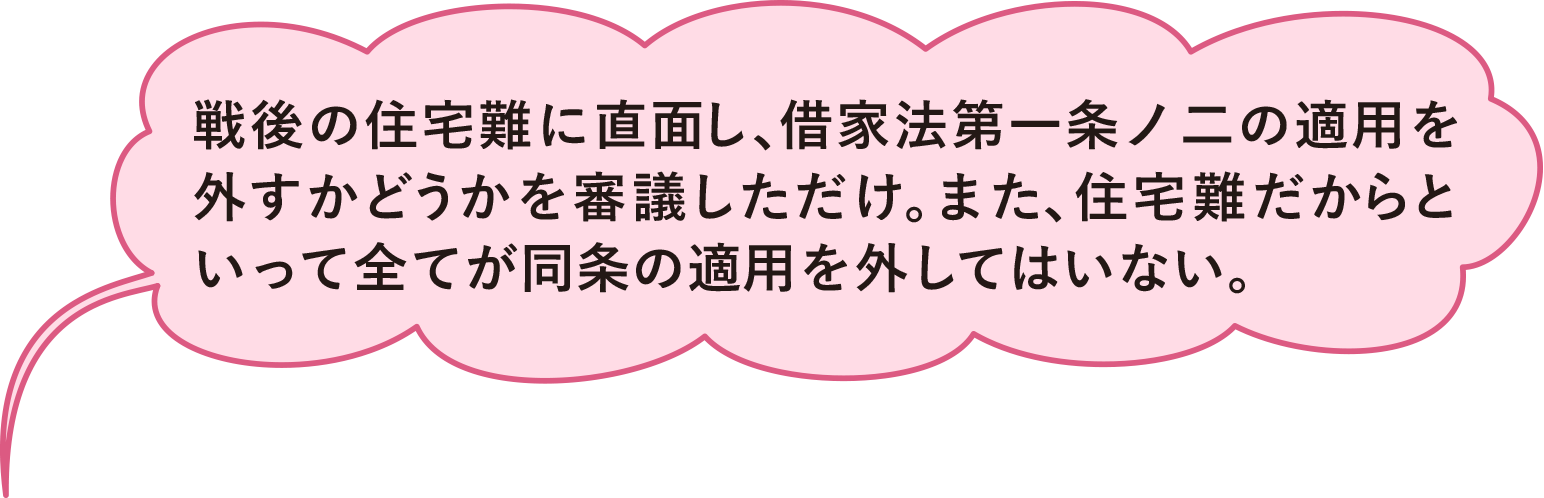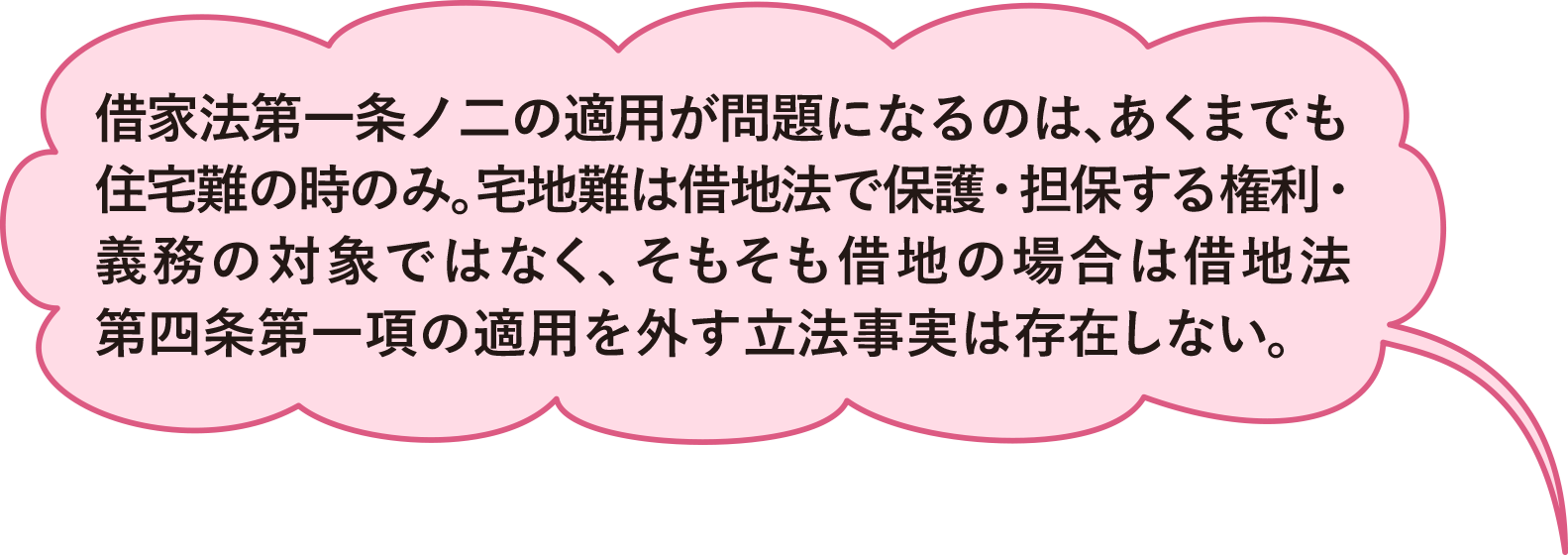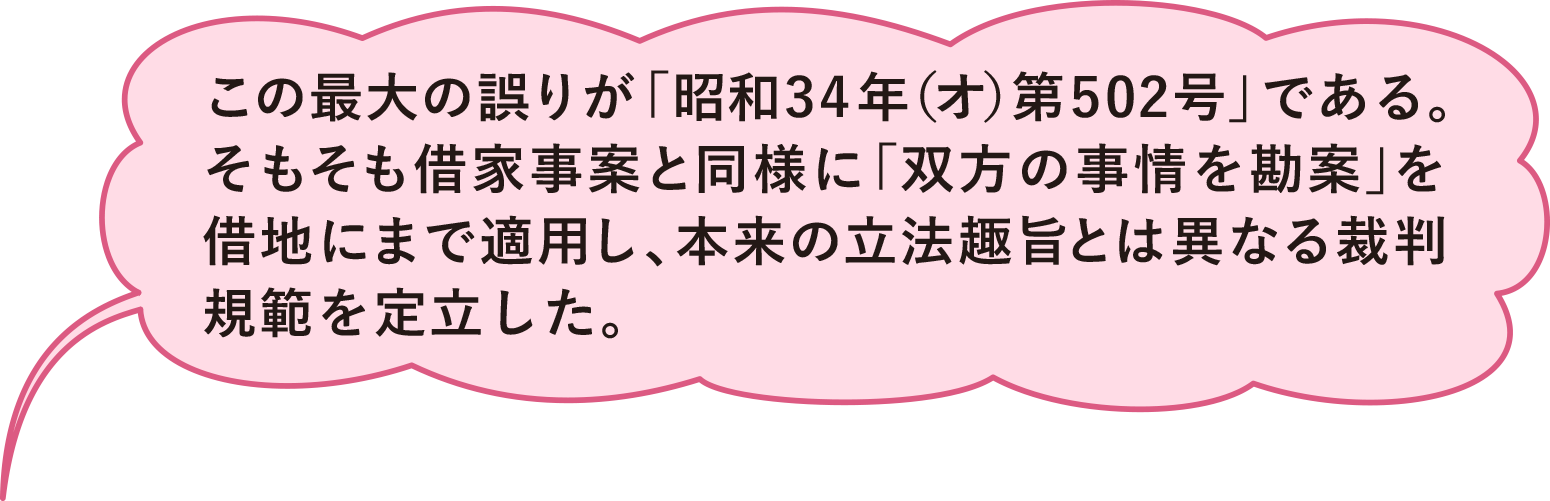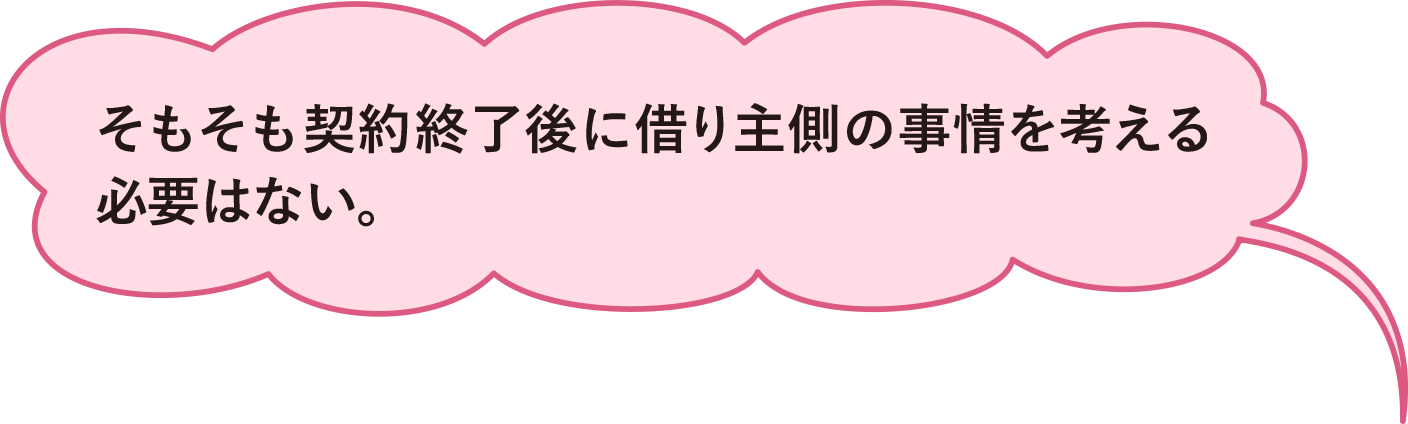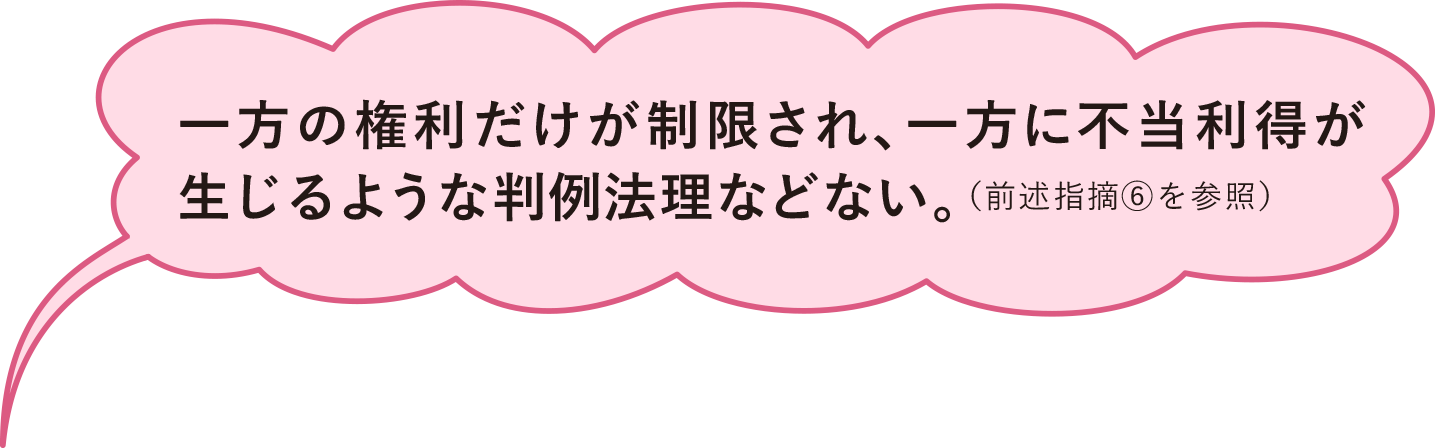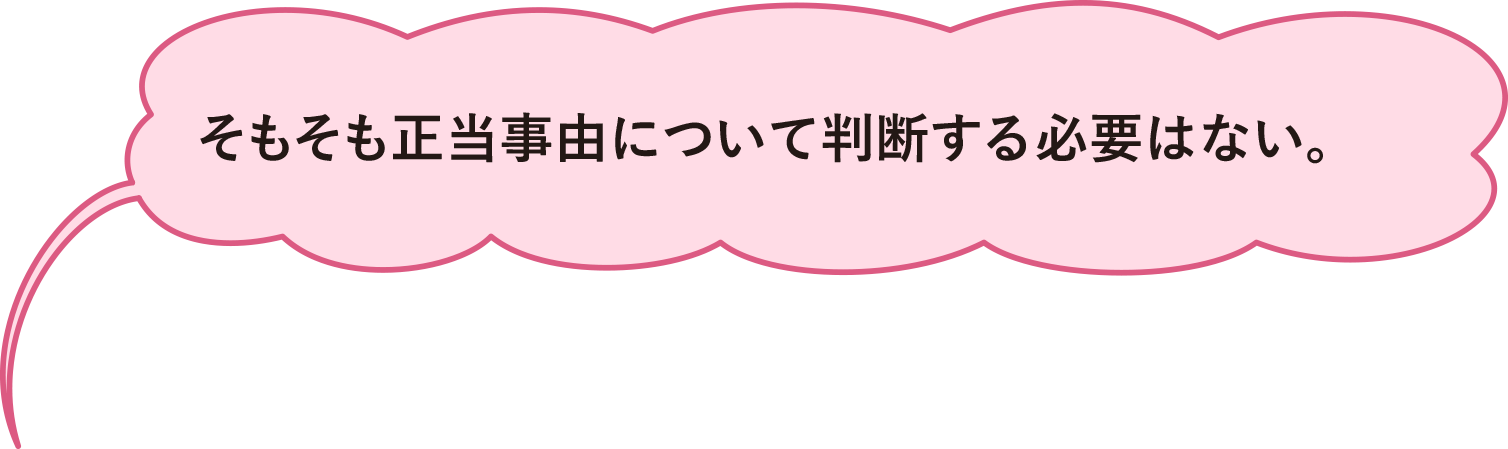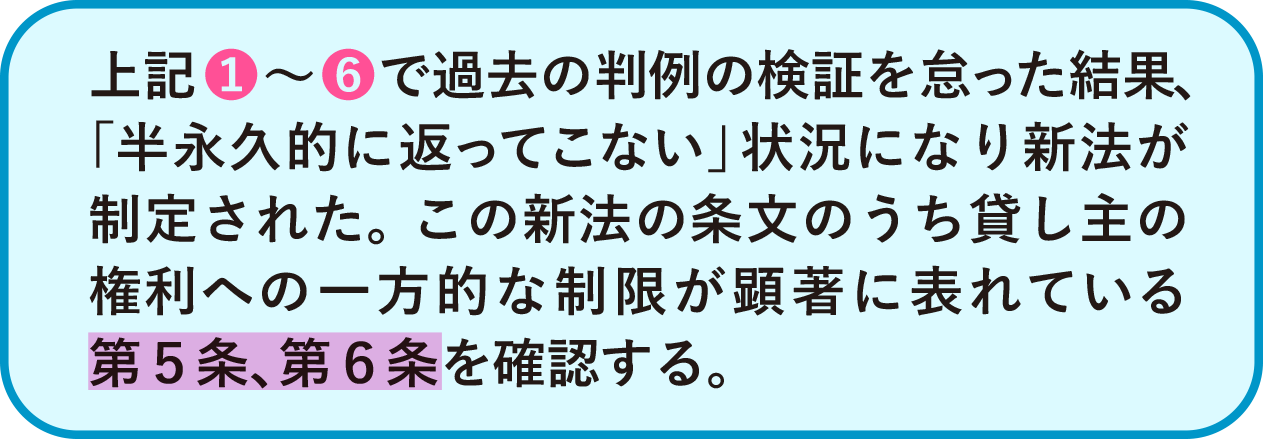第121回国会衆議院法務委員会第2号/参議院法務委員会第4号
借地借家法[平成3年10月4日] 法律第90号:まとめ
以上の検証のとおり、平成3年の借地借家法の制定過程における最大の問題は、先の大法廷判決が生み出した「半永久的に土地は返ってこない」状況に触れつつも、このこと自体が憲法違反であることに国権の最高機関である立法府が気づかなかったことである。
このことは、三権による相互監視と誤りに気づくためのシステムが欠如している証拠である。同時に、これは大法廷判決というものがたとえそれが憲法違反であっても司法内部だけでなく、行政・立法・その他の法律の専門家の判断に対して圧倒的な既判力を持つことを示している。そして、この効力は新法制定後10数年経っても継続している。その証拠が平成18年の小法廷判決である。
このことは、三権による相互監視と誤りに気づくためのシステムが欠如している証拠である。同時に、これは大法廷判決というものがたとえそれが憲法違反であっても司法内部だけでなく、行政・立法・その他の法律の専門家の判断に対して圧倒的な既判力を持つことを示している。そして、この効力は新法制定後10数年経っても継続している。その証拠が平成18年の小法廷判決である。