



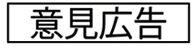
クリックで解説窓が開きます。『注』をクリックで添付資料が別に開きます。
《借地法正当事由研究室》をクリックでホームページに戻ります。
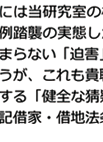
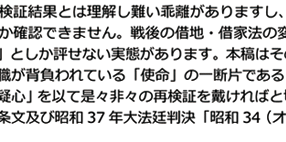
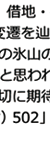
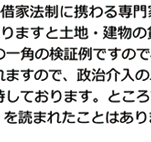
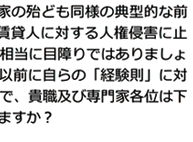
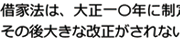
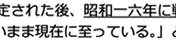

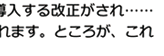

当時は、貸し主の側に使用の必要性があれば、借り主の側の 事情を考慮すること
なく立ち退きを求めることはできるというのが絶対的な条件になっていた】
賃貸借ノ更新ヲ拒ミ又ハ解約ノ申入ヲ為スコトヲ得ス」借家法改正(1941年[昭和16年3月10日]、法律第56号)
【借家法第4条の1】 「借地権消滅ノ場合ニ於テ借地権者カ契約ノ更新ヲ請求シタルトキハ建物アル場合ニ限リ
前契約ト同一ノ条件ヲ以テ更ニ借地権ヲ設定シタルモノト看破ス 但シ土地所有者カ自ラ土地ヲ使用スルコトヲ
必要トスル場合其ノ他正当ノ事由アル場合ニ於テ遅滞ナク異議ヲ述ヘタルトキハ此ノ限ニ在ラス」借地法改正
(1941年[昭和16年3月10日]、法律第55号)
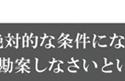
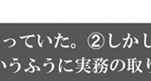
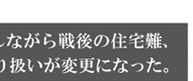
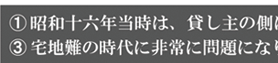
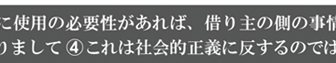
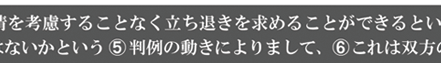
は『借家法第一条の二の規定は……「自ら使用することを必要とする
場合其他」云々と書いてあって、当初は「自ら使用する」場合は絶対
理由と解されて居たのである』と、冒頭①と同一解釈をしている。
続けて「しかし其後漸く住宅難が烈しくなるに従い「正当事由」は
借家人の事情をも考慮し双者必要の程度を比較考慮して決しなければ
いけないと解されるに至り、住宅難の度が増すにつれ右の比較におい
て漸次借家人の方に重さが加わり家主の請求が容易に認められなくな
って来たけれども、立法本来の趣旨は前記の様なものである」として
②④⑤⑥を裏付けた。
二七年(オ)第四四六号」を援用して、「借家法一条ノ二に関する右解釈はなお正
当であると思われる」とした。そうすると、同大法廷河村又介判事も関与され且つ
本来の立法趣旨①を裏付けた前述「昭和23(オ)162」他は縦断的な比較検討から
外されたことになるが、これは単なる調査不足に過ぎないのだろうか。しかも、法
廷更新後の期限の定めのない(一定期間の刑期経過後は何時でも仮釈放請求(明け
渡し請求)が可能な刑事事件)借家事案と、法廷更新後も最低20年から30年を
経過した後も更に同様の正当事由の拘束期間(仮釈放なしの終身刑に等しい)が延
長される借地事案とを何ら躊躇することなく、たった3件の借家判例の裁判要旨を
「コピペ」して憲法適合性を論じた。結果として借地と借家との「比較検討」の必
要を射程外に置いて借家判例の裁判要旨の適用期間を一切斟酌することなく、安直
に「コピペ」したことは立法権を侵害して本来の立法趣旨①に「人権侵害ウイルス」
を埋め込んだことになる。これは、裁判員裁判の量刑に対し判例相場を守れと発し
た最高裁の人権感覚と相入れるのだろうか。
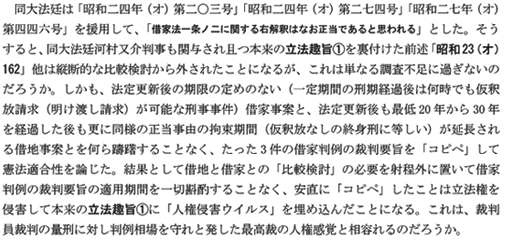
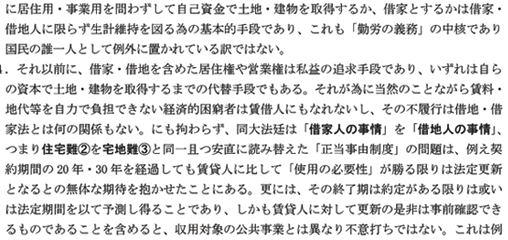
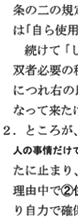
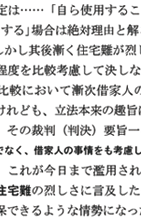
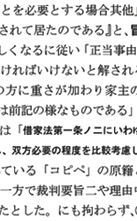

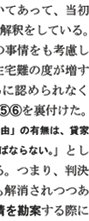
段であり、いずれは自らの資本で土地・建物を取得するまでの代替手
段でもある。それが為に当然のことながら賃料・地代等を自力で負担
できない経済的困窮者は賃借人にもなれないし、その不履行は借地・
借家法とは何の関係もない。にも拘わらず、同大法廷は「借家人の事
情」を「借地人の事情」、つまり住宅難②を宅地難③と同一且つ安直
に読み替えた「正当事由制度」の問題は、例え契約期間の20年・30年
を経過しても賃貸人に比して「使用の必要性」が勝る限りは法廷更新
となるとの無体な期待を抱かせたことにある。更には、その終了期は
約定がある限りは或るいは法定期間を以って予測し得ることであり、
しかも賃貸人に対して更新の是非は事前確認できるものであることを
含めると、収用対象の公共事業とは異なり不意打ちではない。これは
例えるならば、生活保護受給者や公営住宅等の賃借人が⑧一度獲得し
た権能の継続的な保護を顕現しようとするには、「自力で生計維持で
きないこと」や「未だに勤労所得が条件ないにある」ことを例え何年
経過しようとも、その時点で証明可能であればよいとした等の「モラ
トリアム」の督励を導入したと同義でもある。
由」の有無は、貸家人の事情だけでなく、借家人の事情も考慮し、双方必要程度を
比較考慮して決しなければならない。」としたに止まり、これが今日まで濫用され
ている「コピペ」の原籍となっている。つまり、判決理由中で②住宅難の烈しさに
言及した一方で裁判要旨二や理由中で住宅難も解消されつつあり自力で確保でき
る様な情勢になったとした。にも拘わらず、⑥双方の事情を勘案する際には『使用
上の注意』を要する旨の表記の必要は絶対的なものでもあったが……。立法趣旨や
住宅難の緩和については「昭和25年(オ)148」(注6)、「昭和30年(オ)179」
(注7)」でも同様に判じている。これらは、何れも終戦直後の住宅難対策(あく
までも自力での住宅確保が難しい社会実情)として社会法的(災害救助法)観点か
ら、法本来の効能を抑制する「住宅難ワクチン」が処方されたものである。先の東
日本大震災における救済措置(セーフティネット)も、あくまでも被災者が自然災
害で被った損害の原状回復が限界線であり、事業再開資金等の優先貸付や利子補給
等はあるが、それを超えた私的資産形成・私益に対する援助はなされない。また、
都営・民間住宅等を被災地自治体が家賃負担により借り上げた上で、「無償のみな
し仮設」として被災者に供されていた救済措置の打ち切り報道も自立を促す為であ
る旨に言及している。
難しい社会実情に照らし、社会法的観点からの救援策であり、社会情勢
が元に戻れば、この救援対策を終了して自立を促す必要があった。
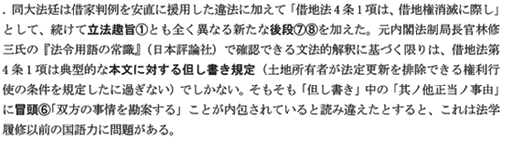
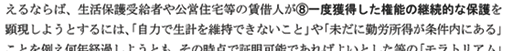
権消滅に際し」として、続けて立法趣旨①とも全く異なる新たな後段⑦⑧を加えた。
元内閣法制局長官林修三氏の『法令用語の常識』(日本評論社)で確認できる文法
的解釈に基づく限りは、借地法第4条1項は典型的な本文に対する但し書き規定(土
地所有者が法廷更新を排除できる権利行使の条件を規定したに過ぎない)でしかな
い。そもそも「但し書き」中の「其ノ他正当ノ事由」に冒頭⑥「双方の事情を勘案
する」ことが内包されていると読み違えたとすると、これは法学履修以前の国語力
に問題がある。
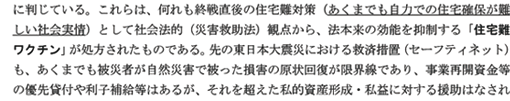
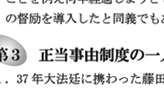
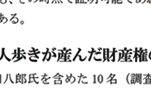
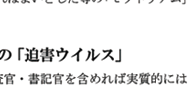

を含めれば実質的には同一大法廷とも云える)は、「昭和29(オ)232」
(注10)で罹災都市借地借家臨時処理法に関する憲法適合性として「そ
して右両条は、前記申出を任意に承諾した場合においても、又、法定期
間内に拒絶の意思を表示しないで申出を承諾したものとみなされる場合
及び拒絶しても正当な事由があると認められない場合においても、いず
れも、相当な借地条件又は対価で敷地の借地権が設定又は譲渡される
(二条一項、三条各本文、一五条、一六条)ものとしているのである
から、憲法二九条三項にいわゆる正当な補償なくして財産権を侵害す
るものとは認められない。」と判じた。罹災法第2条の3に規定されて
いる正当事由は、借地法4条1項が「土地所有者カ自ラ土地ヲ使用スル
コトヲ必要トスル場合」に「建物所有の目的」を加えたものである。
つまり、実質的には同一の正当事由とも云い得る規定の適用に関して、
37年大法廷が憲法29条3項の「補償の必要」を審査しなかったことは
理解し難いものがある。
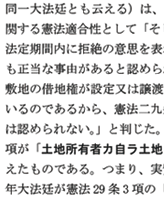
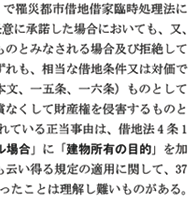
が導き出されるのであろうか。しかも、土地・建物の⑦所有権本来の権能のの収受権一は
物件から産み出される利益の独占的収受権にあり、借家権・借地権の本質もその賃貸借契
約に基づく権利に過ぎない。逆説的ではあるが居住用建物は労働対価を以って回収せざる
を得ないが、事業用建物投下資本の回収原資はその土地から産み出される収益であり、建
物はその回収装置に過ぎない。大正10年の借地借家法制定時の施行地区も、既に利用価
値の集積が顕在化している地域が対象である。また、⑧一度獲得した土地使用の権能の保
持に関しても、契約期間中の賃貸人の権利濫用から保護する必要は当然にある。借地・
そもそも私法契約に関わる立法本来の目的は、借家法に限らず双方が約定に基づ権利義く
務の履行の秩序を担保することは「公共の福祉」の本旨ではあるが、この正当事由制度は
その境界線を著しく超えている。
また同大法廷の河村又介・石坂修一の両判事は「昭和34(オ)326」(注9)で「居住
権および生活圏は、上告人が本件土地に居住する権原があることを前提とするものであ
る」と一般条項を説かれている。つまり、借地人は契約期間満了を以って権原が消滅した
場合でも、建物等投下資本の未回収分を含めて「建物買取請求権」の行使により清算でき
るはずである。
しかも、立法趣旨①を正解する限りは、契約消滅期は当然に確定していることから、
その後に居住用・事業用を問わずして自己資金で土地・建物を取得するか、借家とするか
は借家・借地人に限らず生計維持を図る為の基本的手段であり、これも「勤労の義務」
の中核であり国民の誰一人として例外に置かれている訳ではない。
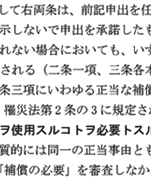
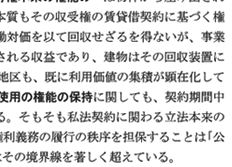
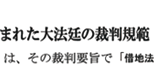
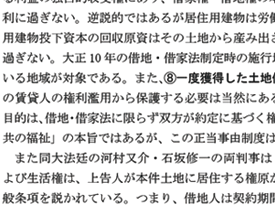
旨で「借地法第四条第一項は、憲法第二九条に違反しない。」と判じた。同大法廷
が定立した裁判規範が立法趣旨①とは似て非なるものであることは、冒頭①~⑥の
経緯を知らなくとも或いは立法時の議会議事録を紐解かなくとも、初歩的な国語力
で当該条文の本旨は解読できたはずである。
しかも同大法廷の審理は前掲の借家判例時とは全く異なる世相下で行われてお
り、社会的事情に引きずられるような渦中に置かれていたわけではない。ちなみに
昭和37年3月に司法研修所は『法令・判例・学説の調査について』の42頁で「あ
る裁判がはたして判例であるかどうか、あるいは数多の裁判のうちどれが判例なの
かは、実は当該裁判を中心にしていえばその前・後の多くの裁判を比較検討するこ
とによって(・・・縦断的に・・・)はじめて決せられるのである」とした。
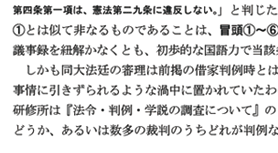
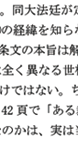
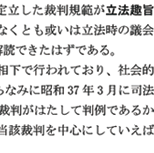

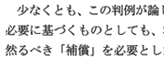
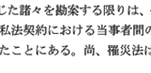
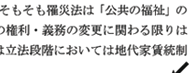
は「公共の福祉」の必要に基づくものとしても、私法契約における当事
者間の権利・義務の変更に関わる限りは然るべき「補償」を必要とした
ことにある。尚、罹災法は立法段階においては地代家賃統制令の廃止を
前提として決議されたが実際には排されていない。つまり罹災法判決は
賃貸人と借地人との権利金の授受が禁止されている事実を見落としてい
る。これに関して、昭和24年5月30日付の吉田内閣が発した質問主意書
に対する答弁書第94号(注11)で「新借地人が前借地人に対して『権利
金』を支払うことは禁止しておりません。」とし、その後段で権利金等
の取り扱いが「均衡を失する憾み」があると事後の検討の必要を明記し
た。この答弁書は内閣法制局関与によると思われるが、少なくとも権利
金等を一切負担していない借地人が第三者に対する譲渡代金を受領する
ことの(しかも契約残存期間をも一切問うことなく)本質的な問題点は
抽出し得たはずである。ところが、罹災法立法時や、昭和41年の非訟
制度や平成3年新法の改正制定時にも、加えて一連の大法廷判決でも土
地所有権者の財産権侵害であり借地人の勤労に基づかない不当利得の始
まりでもあることにも誰一人として射程に入れた者はいないし、内閣
法制局だと思われる回答書中の「検討」は不履行となっている。つま
り、この罹災法及び同判決も37年大法廷も、何れも憲法適合性を維持
し得ない違法立法及び判決である。
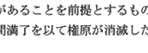

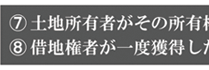
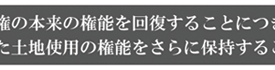
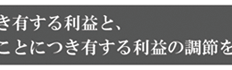


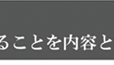

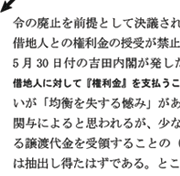
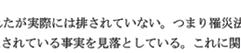
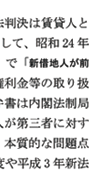

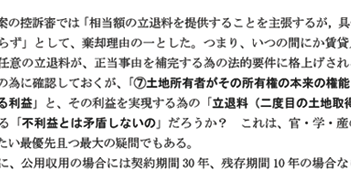
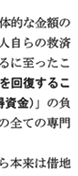
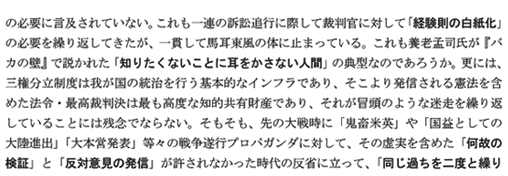
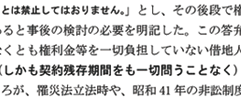
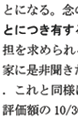
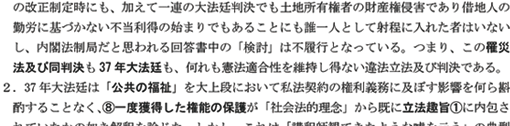
本来は借地評価額の10/30となるはずにも拘わらず借地権評価額の全額が補償対
象となる。国税庁の評価規定(注14)では、残存期間30年の地上権割合は40%、
10年以下で5%となっている。同様に定期借地権の場合は残存期間15年を超える
もの20%、10年以下で10%、5年以下で5%とされている。つまり、新法と旧法
との借地権評価において、これだけの格差が生じていることに対して、鑑定士や
弁護士等の士業専門家は何故に何ら疑問も抱かなかったのだろうか。
それともこの実態を知らなかった?或いは、この程度の格差では土地賃貸人
の財産権を「迫害するとまでは云えない等の何らかの根拠・理由があったの」
だろうか?
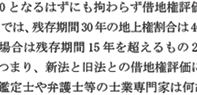
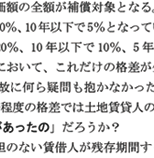
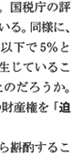
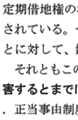
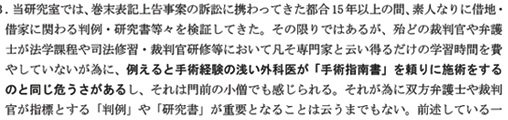
以上の間、素人なりに借地・借家に関わる判例・研究所等々を検証し
てきた。その限りではあるが、殆どの裁判官や弁護士が法学過程や司
法修習・裁判官研修等において凡そ専門家と云い得るだけの学習時間
を費やしていないが為に、例えると手術経験の浅い外科医が「手術指
南書」を頼りに施術をするのと同じ危うさがあるし、それは門前の小
僧でも感じられる。それが為に双方弁護士や裁判官が指標とする「判
例」や「研究所」が重要となることは云うまでもない。前述している
一連の経緯実態は、三権分立制度の根幹を揺るがしかねない事態で
もあると考えられるのであるが、それにも拘わらず司法・行政・学
会・日弁連を含めた士業集団・産業界の誰一人としてこの憲法適合
性に対する疑問が提起されることなく今日に至っている。この一連
の不作為そのものの源流を辿ると、そこには法学教育において初歩
的な「確かめ算」の必要が履修されていないこと、「詰め込み教育」
の弊害かとも云える「師」や「教科書」の刷り込みに染まり過ぎ、
これら先人の教えを微塵も疑う学習姿勢が体得されていないのかと
いう感がある。しかも前段①~⑧に関しても初歩的な論理関数
「IF・AND・OR」に委ねれば、その是非は自明のことと思われる
のであるが。マイケル・サンデルは白熱教室でセルフ・ディベート、
つまりは自らの「ボケ・突っ込み」の効用を説いたものと考えら
れるが、前述したように本件に携わった法医学者・専門家・建物の
論旨にはその痕跡すら窺えない。そればかりか、これは土地・
建物の賃貸人に対する「人権侵害」であるにも拘わらず、法務省・
人権擁護局の役割が全く見えてこない。これも省内に「縦割り社会」
があるのかと揶揄したくなるのだが。
影響を何ら斟酌することなく、⑧一度獲得した権能の保護が「社会法的理念」から
既に立法趣旨①に内包されていたかの如き解釈を論じた。しかし、これは「講釈師
観てきたような嘘を云う」の典型でもあり、この⑧は大法廷による看過してはなら
ない「捏造」でもある。しかも⑧の概念を源泉として、社会的弱者でもない借地・
借家の賃借人保護の必要が社会法的な観点から語られ、その手段として土地・建物
の賃貸人に限っては、一般的な土地所有権者と比較考量しても理解し難い拘束が課
されることになった。昭和16年改正法冒頭の「自ラ土地ヲ使用スルコトヲ必要ト
スル」も、戦時体制下故の事情として許されるとしても、「⑦所有権本来の権能」
とは「処分の自由」であり今日の社会情勢下においては一般的な所有権と比較する
と差別的条文でしかない。前述したように37年大法廷が立法趣旨を改竄・捏造し
て定立した正当事由制度の反面的問題は「モラトリアム」の督励としか解せない無
体な期待権を借地・借家賃借人に抱かせたことにある。今日に至る一連の経緯を振
り返ると、借地・借家法に携わる官・学・産の専門家が然るべき初歩的な注意を以
て検証すれば、その不作為の連鎖による違法を覚知し得たはずである。ところが、
殆どの専門家が本来の立法趣旨とは大きくかけ離れた裁判規範を何の疑いもなく
諾々と追認、つまり「コピぺ」から転記された「カンペ」を丸読みしたアナウンス
役を担ってきている。
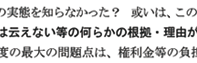
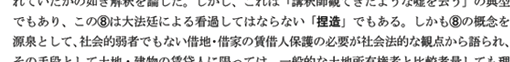
斟酌することなく、しかも契約期間中の支払賃料総額の何百倍もの「労働対価とは
程遠い立退料」を手にすることの「不当利得」にある。そもそも借地の場合に限っ
ても、契約期間中において僅かな地代の負担で賃借物件が生み出す利用権・収益権
を独占してきたにも拘わらず、明け渡しに際しては立退料を必要とすることを創作
した官・学・産の専門家は公平・公正の概念を何処に置いていたのだろうか。加え
て、裁判所が和解勧告を多用して専ら賃貸人に対して「立退料の増額」を進言・指
導して類似事案の解決に繋げてきたことに関しても、これが善意であることは疑わ
ないとしても、自らの不知を含めた経験値に一片の疑いも持たずに「正義」を強い
ることの怖さは一連上告事案で否応なく感じたことでもある。目の前の当事者の痛
みに関する感受性は、法律学で育まれることは無いと思うのだが。
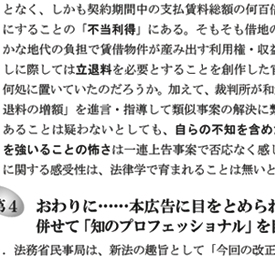
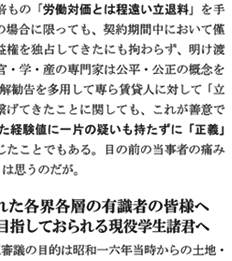
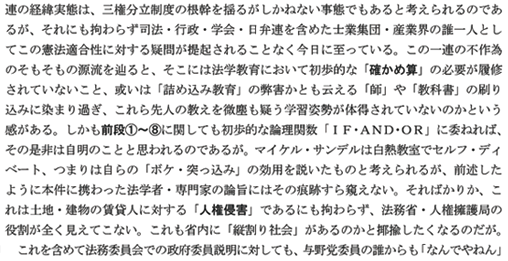
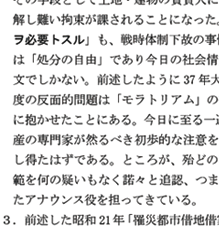
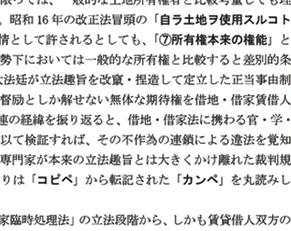
誰からも「なんでやねん」の突っ込みもない上に、少なからぬ野党議員
の初歩的な憲法認識すら埒外に置いた「論語読みの論語知らず」としか
評せない討弁が多々散見されている。更には、報道機関や専門出版社の
著作物に置いても、この正当事由制度の再検証の必要を踏まえた報道・
記事が全く成されていないと云っても過言ではない。ここにも人権感覚
の欠落がある。各位に改めてお願いしたいのは、本稿は「疑う」ことを
知らない、或いは「反対解釈」の「確かめ算」を怠った専門家集団の不
作為を提起したものであるので、本稿全ての論旨を「疑って」みて頂き
たい。
当然のことながら頁容量の関係で全ての事実関係の展開には限界があ
るので、ここでは問題のインデックスを提示したに過ぎない。詳細は当
研究室のHP 注記資料を含めて開示しておりますのでご参照下さい。こ
れ以降は、各界各層各位の「ノブレス・オブリージュ」の精神に勝手な
がら委ねさせて頂きたい。また、法学履修の途上にある現役学生の諸君
には当研究室のHP に巻末表記上告事案の上訴理由書・判決書も開示し
ているので、所属するゼミでの判例研究や模擬裁判等において是々非々
の検証、つまりは、大法廷を含めたこんな「判決」を書かない裁判官や
書かせることのない「弁護士」となるには、既存の法学に何を足して履
修したらいいのか。それに加えて、司法制度を含めた三権システムが
このままで良いのかを「大人」に染まる前に是非「考えて」みて下さ
い。切に、お願いしたい。その上で本年度歌会始で神奈川の15歳中学
生・小林さんが詠んだ歌「この本に全てがつまっているわけぢやない
だから私が続きを生きる」を贈りたい。これは詠み手の意図とは異な
るとしても、温故知新の本質であり、遺伝子、つまり次世代へ手渡す
べきバトン(遺伝子)の進化・変化に必要な要素でもあり、生きとし
生けるものの宿命でもある。
賃貸借人双方の権利・義務の帰趨に最も大きな影響を及ぼす「投下資本の保護」の
概念が専ら借地人の視点に止まっていることにも理解し難い不作為がある。その最
大の問題点は、戦前戦後の「強制疎開」や「接収」に際して「残存契約期間」を一
切問うことなく「借地権の補償」が行われているが、今日の都市計画における「収
用補償」にもこれが何の疑問もなく同一基準で施行されていることである。本来な
らば工学、つまり最も科学的見地を求められているはずの「鑑定士」でも、教えら
れていないが為であろうが「何の疑問」もなく権利金の有無や残存期間を全く斟酌
することなく借地権の評価を繰り返している。昭和14年の地代家賃統制令は借
家・借地の別なく権利金等の授受は禁止しているが、第51回国会衆議院法務委員
会(注12)で当時の新谷法務省民事局長は「東京におきましては三千七百七十三
件調査……九.八%が権利金の授受がある。……これは大正年間あるいはそれ以前の
ものから昭和三十七年に至りますまでの調査の結果の集計……。」と説明している。
これは統制令による権利金禁止と、立法趣旨①の通り契約満了期には貸付地を還し
てもらえることに依拠したものであることに法務委員は気づくべきであった。つま
り立法実務者や立法府・それを補佐する内閣法制局が「権利金授受の実態の少なさ」
から、「借地権を物権的に取り扱うことの危うさ」は予見し得たと思うのだが。
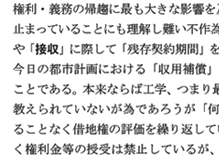
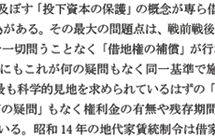
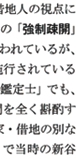
住宅事情の変化に照らし、当事者間の利害の公正公平な調整という見地から現行法の不合理・
不都合な点を見直す事にある。」とした。これは現在に至る間の②③に関する事情変化とする
とむしろ一刻も早く⑥の正当事由制度を大法廷で変更する必要が④社会的正義の観点から優先
されるべきと思われるのだが。ところが加藤一郎氏は(注15)で「最近、新規の借地はほとん
どないという状態になった。それは一度貸したらもう返らないというような意識が土地所有者
の方にございますので……新しく貸す人がなくなってきているというのが実情でございます……
そこで出てまいりましたのが更新のない借地権です。定期借地権は、最低二十年から三十年と
いうふうになっている、更新がないからそこで土地は必ず戻ってくる」と学識者としての見解
を説明されている。しかしながら、そもそも一方当事者の異議権を強制排除することによる終
期のない私法契約が有っていいのか。加藤氏と同様の新法制定趣旨は民事局当事者は当然
に、国務大臣や法務委員会委員長も述べている。この実態は何れも誰一人として条文のオリジ
ナルを確認すること無く、専ら「コピぺ」に基づき事務方が作成した「カンペ」を丸読みし
たに過ぎない。政治家は兎も角としても、嘗ては東大総長までされた不法行為の専門家でも
ある加藤氏の初歩的な法概念の欠落は、決してあってはならないはずである。なお、加藤一
郎氏は東大教授時代にも昭和41年の非訟制度に拘る法改正に際して、この借地法を「終わり
のない契約である」(注16)として8条・9条がもたらす土地所有権者に対する「不利となる
恐れはない」ことの裏付けとしているが、これは違憲立法の共同正犯とも云える。少なくと
も寺田長官と同様に加藤一郎氏も関係者として法制史に言及されるに際して、借地・借家の
条文や昭和37年大法廷判決を確認されたのであろうか? ご両者を始めとした官・学・産の
専門家が発信された著作物からは、その痕跡が一切窺えない。
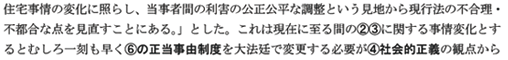
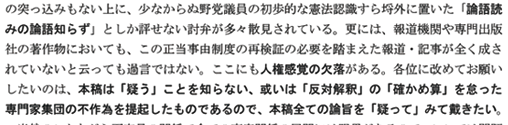
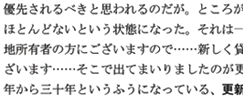
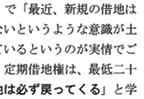
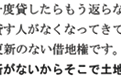
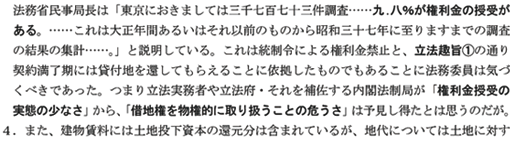
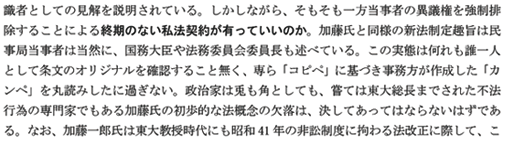
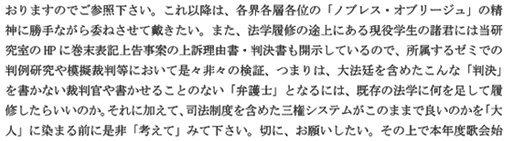
ともなる還元分は含まれていないし、権利金は土地投下資本に対する借地人の分担とも言える。これが如何なる問
題を生じるかというと、37年大法廷が定立した正当事由制度では契約期間満了による借地権消滅の場合でも、何故
か借地権消滅の対価として立退料の負担を強制的に求められる。この立退料については、「昭和25(オ)108」
(注13)で「被上告人が、立退料の金額を示して立退を懇請しても、上告人がこれに応じなかったことが窺える」
とした。これは、立法趣旨とは異なる正当事由制度の硬直的な運用に対して、その補償を任意負担しても明け渡
しを求める必要を優先した賃借人の選択に始まったものである。
第一上告事案の控訴審では「相当額の立退料を提供することを主張するが、具体的な金額の提示をしておらず」
として、棄却理由の一とした。つまり、いつの間にか賃貸人自らの救済処置としての任意の立退料が、正当事由を
補完する為の法的要件に格上げされるに至ったことになる。念の為に確認しておくが、「⑦土地所有者がその所有権
の本来の権能を回復することにつき有する利益」と、その利益を実現する為の「立退料(二度目の土地取得資金)」
の負担を求められる「不利益とは矛盾しないの」だろうか?これは、官・学・産の全ての専門家に是非聞きたい最
優先且つ最大の疑問でもある。
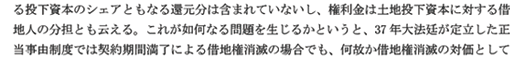
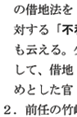
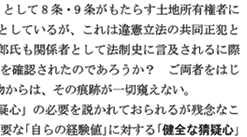
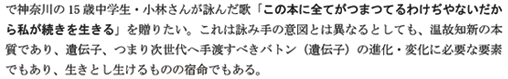
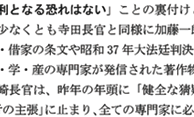
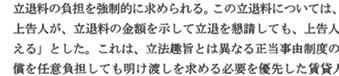
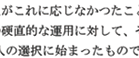
「立ち位置・見取り図」を一切示すこともなく「立憲主義に反する」
を唱えている。その集団知に問いたいのは上記①~⑧は「立憲主義
に反しない?」、それとも「所掌範囲ではない?」、或いは「知ら
なかった?」……のかと。
全ての専門家に必要な「自らの経験値」に対する「健全な猜疑心」の必要に言及されていない。これも一連の訴訟追行に際して
裁判官に対して「経験則の白紙化」の必要を繰り返してきたが、一貫して馬耳東風の体に止まっている。これも養老孟司氏が
『バカの壁』で説かれた「知りたくないことに耳をかさない人間」の典型なのであろうか。更には、三権分立制度は我が国の
統治を行う基本的なインフラであり、そこより発信される憲法を含めた法令・最高裁判決は最も高度な知的共有財産であり、
それが冒頭のような迷走を繰り返していることには残念でならない。そもそも、先の大戦時に「鬼畜米英」や「国益としての
大陸進出」「大本営発表」等々の戦争遂行プロパガンダに対して、その虚実を含めた「何故の検証」と「反対意見の発信」が
許されなかった時代の反省に立って、「同じ過ちを二度と繰り返さない」ことを戦後の国是としたはずである。しかも、立法・
行政・司法の三権に委ねられたその責任の重さは一般国民の比ではないと思われるのであるが……。